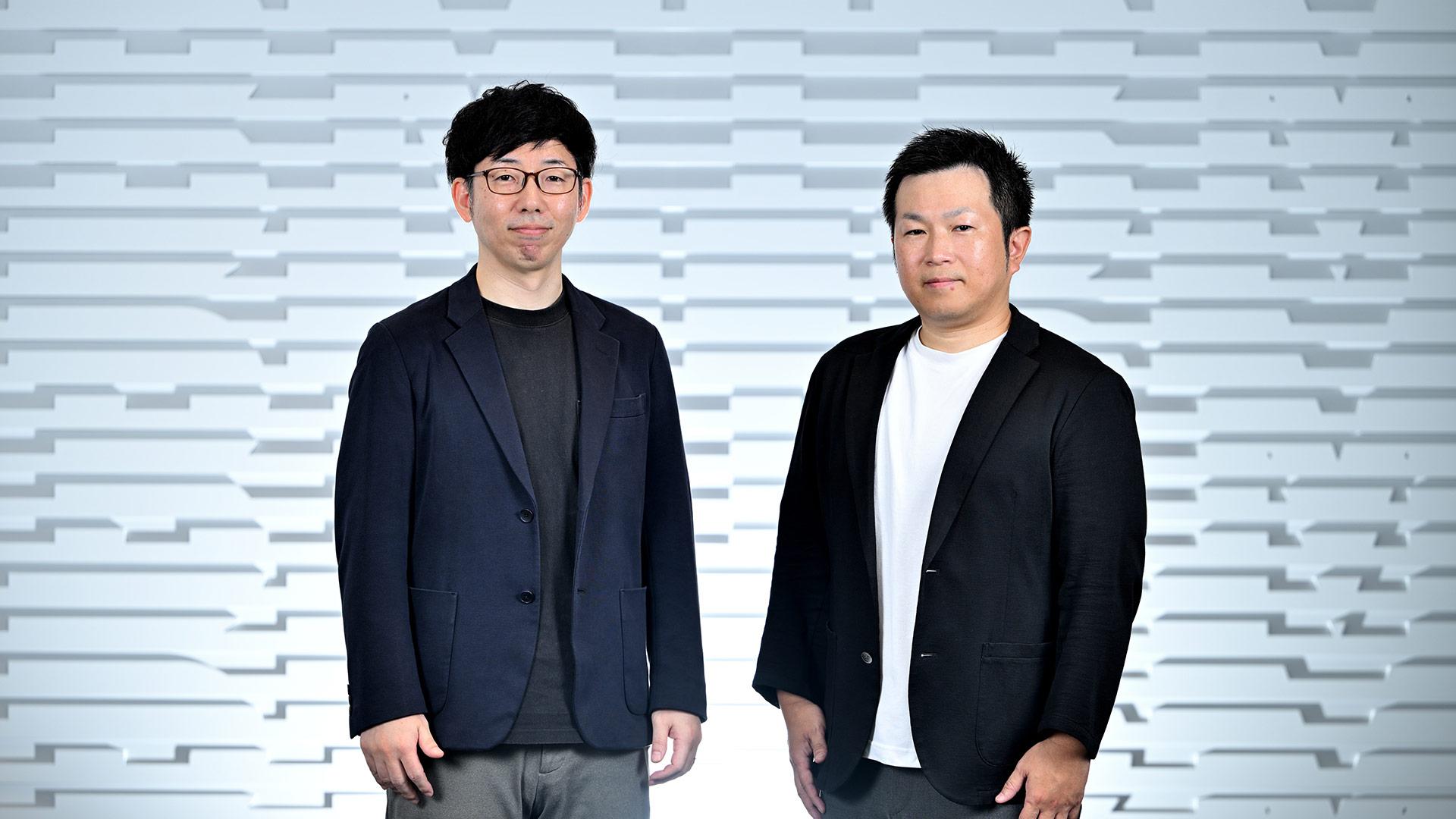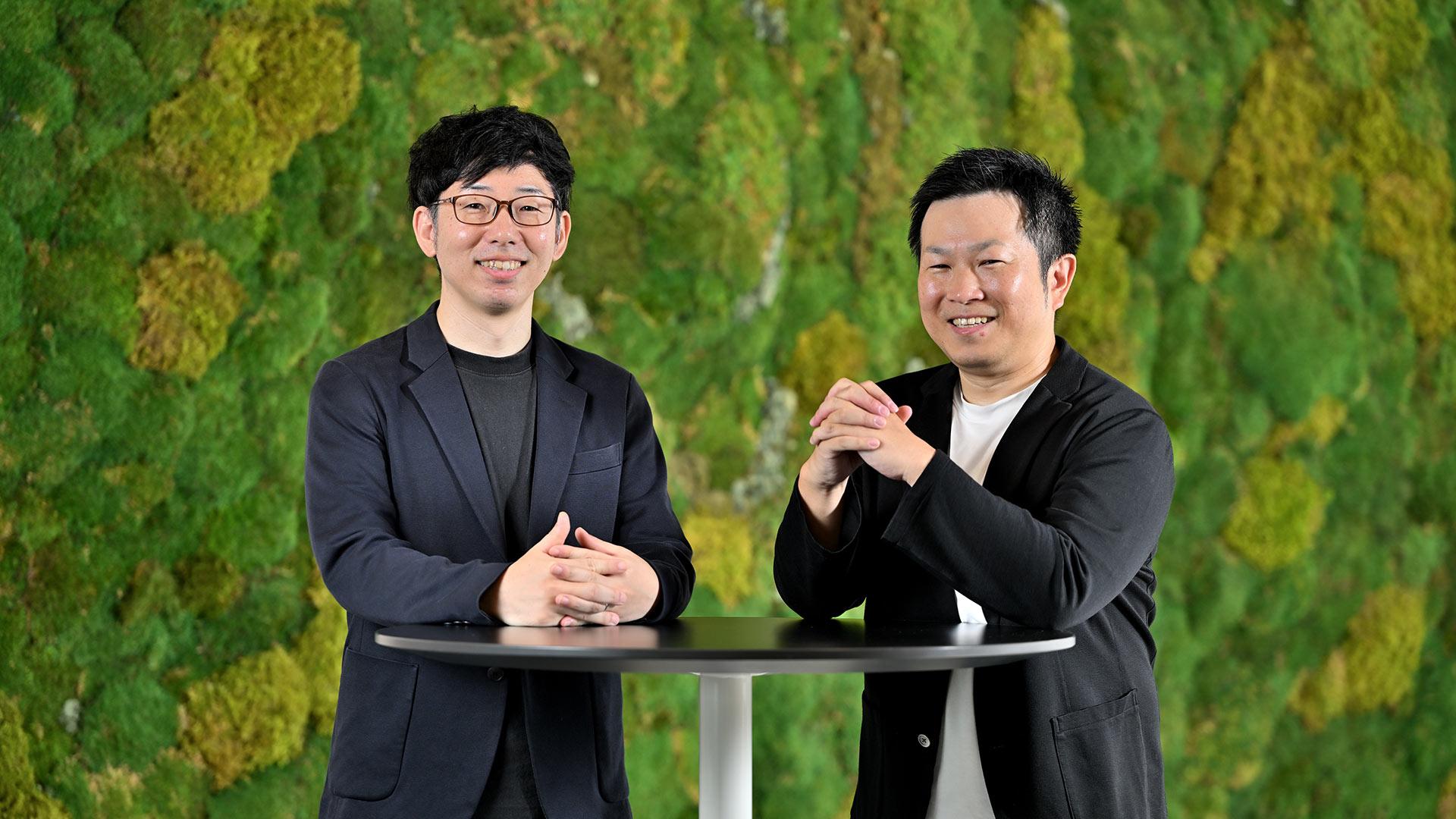システム全体最適化と一体で進める共通AI基盤の整備 |ふくおかフィナンシャルグループのDX最前線
- ありがとうございます!
- いいね!した記事一覧をみる
付加価値領域に注力すべくシステムの全体最適化を推進

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
DX推進本部 システム設計グループ
主任調査役

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
DX推進本部 システム設計グループ
調査役
2025年からスタートした第8次中期経営計画では、「経済的・物質的・精神的にゆたかな地域社会」の実現を目指し、既存ビジネスの変革や新たな価値創造、強靱な基盤づくりなど5つの基本方針を掲げています。これらを支える上で欠かせないのがシステムの全体最適化です。
背景にはIT部門が抱える課題認識があります。昨今、デジタル化の進展に伴ってシステム化案件の数が増加の一途をたどる一方、IT人財の育成や採用は容易ではありません。その結果、本来の業務に注力しにくくなり、システムの個別最適化や機能の重複といった課題が見られるようになってきました。
「今はシステムがなければビジネスが成り立たない時代です。システム自体がビジネス価値を創出していけるようなかたちを目指すべきであり、そのためには自分たちの仕事をより付加価値の高い領域にシフトしていく必要があります」と大上氏は話します。
このためFFGでは、大上氏らが所属するシステム設計グループが中心となり、システムの企画段階から全体最適を意識して取り組む体制づくりを進めています。業務や最新技術への理解を深めながら最適化を推進することで、今後の全社的なAI活用を支える基盤を作ることを目指します。
この全体最適化の取り組みは「体制・人財」「プロセス」「ナレッジ・アセット」「共通インフラ」の4つを柱としており、共通インフラに関しては全体最適化に必要なAPIや共通AI基盤の整備を行っています。
全社的なAI活用を支える共通AI基盤を整備
こうしたAI活用戦略を支えるのが共通AI基盤ですが、整備の発端となったのは“AI乱立の防止”でした。
「生成AIの台頭に伴い、さまざまなベンダーからAI導入の提案が寄せられ、社内の各部署からも『AIを導入したい』という相談が増えてきました。それらに個別に対応し続けることで、コストの増加や開発の重複といった無駄が生じやすい状況になりつつありました」(大上氏)
共通AI基盤には、それを防ぐ役割があります。同基盤には、文章の要約や翻訳などの基本的なAI機能(タスクAI)が備わり、これらを各システムから利用することで開発スピードの向上やビジネス・アジリティーの強化、最先端AI技術の速やかな導入、ガバナンス強化といった効果が期待できます。将来的には、自行で開発したタスクAIを外部に提供し、サービス化につなげることも視野に入れていると大上氏は話します。
また、共通AI基盤の構築にあたってはアーキテクチャー設計にも工夫を凝らしました。既存システムを構成する「画面入出力─業務ロジック─データ」に対し、共通AI基盤は「業務ロジックを補完してより高度化するもの」と位置付けています。共通AI基盤側に複数のタスクAIと大規模言語モデル(LLM)を用意し、各システムが用途に応じて柔軟に切り替えて使うことができます。さらに、AIアプリケーションの多様性を受け入れ、AIの可能性を最大化するために、フロントシステムとタスクAIの間にAPI層を設け、このAPI層をハブとして多様なタスクAIを受け入れられるアーキテクチャーとしています。
業務部門が使えるAIアプリケーション開発環境「Dify」を導入
Difyを活用した共通AI基盤により、AI活用に伴うさまざまな課題を解決できると中山氏は話します。
「従来は投資対効果(ROI)が見えづらい要望や机上での検討にとどまらないフィージビリティー検証を行うことが難しく、生成AIの可能性を十分に探るには一定のハードルがありました。Difyを共通AI基盤に導入することで、これらの課題を解消し、新たなニーズに対して迅速な検証が可能になると期待しています」
検証スピードはどの程度向上するのでしょうか。これまではPoCや実証実験を行う際、ベンダー選定や予算確保・契約、本番導入時の予算確保・契約などに多くの工数を要していました。共通AI基盤でそれらを省略でき、PoCから本番導入までを大幅に短縮できるようになります。
共通AI基盤の整備以降、FFGにおけるAI活用は一気に加速しており、現在は複数の案件が並行して進んでいます。「半分以上はITエンジニアではない業務部門の社員が自ら作成し、やりたかったことを実現できています。また、Difyを安全かつ継続的に活用するためには、(1)全体運営、(2)案件推進、(3)開発・教育、(4)運用保守の各領域で体制整備が不可欠でしたが、日本IBMにはその導入に向けたコンサルティングなど、当行の立場に寄り添った積極的な提案と手厚いサポートをいただきました」と中山氏は話します。
デジタル基盤の整備はアーキテクチャー、データ、AIの三位一体が鍵
中山氏は、共通AI基盤のようなデジタル基盤の推進では、「システム・アーキテクチャーとデータ、AIを三位一体で進めることが重要」と強調します。
「システム・アーキテクチャーを最適化し、AIを適材適所で活用しながらデータを蓄積する好循環を回すことで、ビジネスを加速度的に進化させることができます。AI活用には整ったデータが不可欠といった声も耳にしますが、当社ではAIを使いながらデータを蓄積するというアプローチも取り入れ、今後もAIの活用を広げていきたいと考えています」(中山氏)
ビジネスのためのAI
詳細はこちら:
https://www.ibm.com/jp-ja/products/watsonx-orchestrate
AI導入のためのコンサルティングサービス
https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/artificial-intelligence