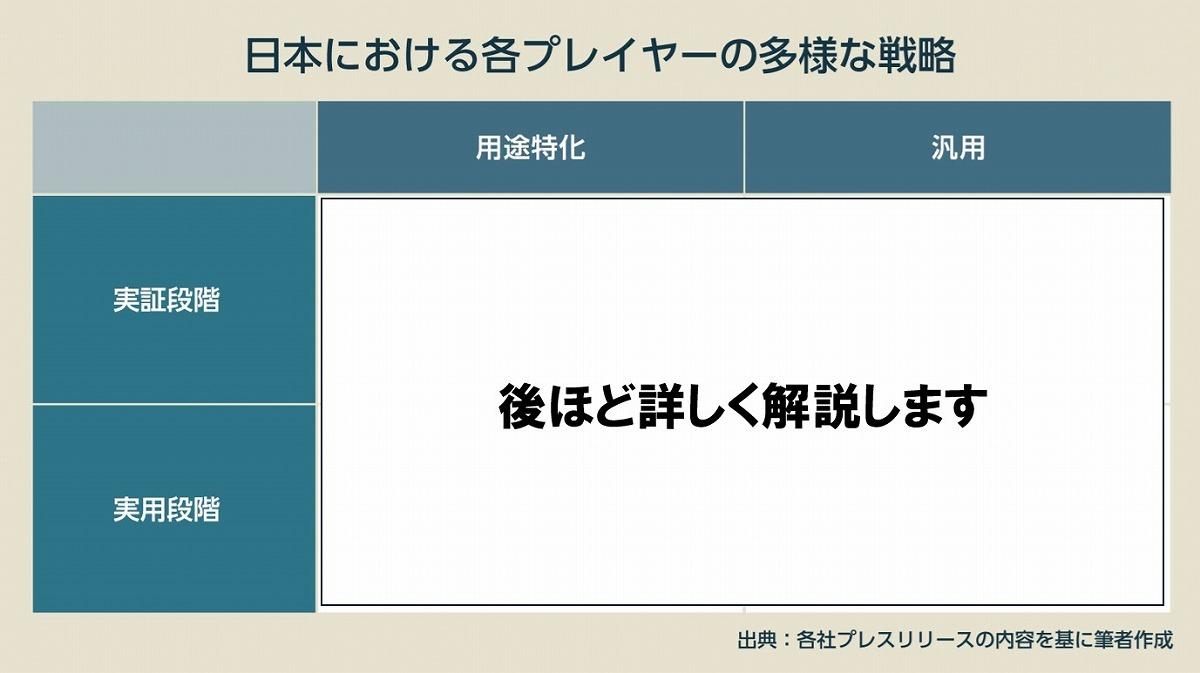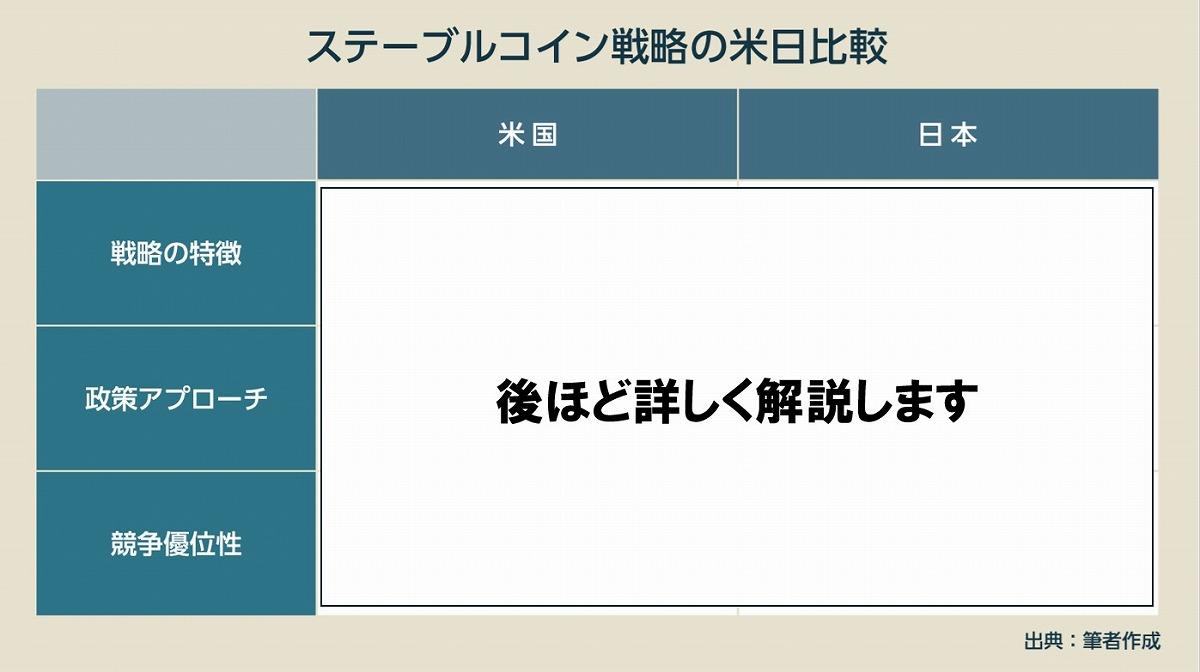- 会員限定
- 2025/08/28 掲載
米国は「ステーブルコイン財政」、では日本は? ソニー銀や北國銀など4社の戦略
NTTデータに新卒で入社、金融機関向けのシステム開発に従事した後、メガバンクのITグランドデザイン策定プロジェクトに参画を機にコンサルタントとしてのキャリアをスタート。金融機関のIT戦略、テクノロジー戦略、テクノロジー起点の事業創造などを主なテーマとしてとりあつかう。情報発信も積極的に実施しており、「Web3と自律分散型社会が描く銀行の未来」(金融財政事情研究会)などの著書や雑誌への寄稿も多数。
NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室 フォーサイト担当 橋本 響太 2025年、株式会社NTTデータに入社。これまでに、中央省庁やスタートアップ、シンクタンクにて、主に金融と先端技術の交叉する領域でのリサーチや執筆、新規ビジネス企画などに携わる。
ソニー銀行のエンターテイメント特化戦略
前編では、米国の「財政戦略」としてのステーブルコイン推進、そして日本における第一陣の事例としてProgmat・三井住友FGの動きを紹介した。後編では、ソニー銀行のエンタメ経済圏戦略、みんなの銀行のBaaS展開、北國銀行の地域キャッシュレス化、JPYCの先行者戦略など、日本各社の多彩なアプローチと、米国モデルとの対比を掘り下げる。まず、ソニー銀行だがそのアプローチは独特だ。2024年4月、ブロックチェーン開発プラットフォームのポリゴン・ラボ、ブロックチェーン開発ツールを提供するセトルミントと、ステーブルコインの発行に向けた実証実験を開始(注1)。同年7月にweb3エンターテインメント領域向けアプリ「Sony Bank CONNECT」をリリース(注2)。
本年6月には、シンガポールのブロックチェーン開発企業コーシーとともに、ステーブルコインの利活用に特化した独自チェーンの実現などをテーマとした実証実験を始める(注3)など、矢継ぎ早にステーブルコインに関する取り組みを進めている。
同社は、ソニーグループの知的財産を活用したクリエイター・ファンweb3経済圏での決済手段として、ステーブルコインを位置づけているとみられる。実際、ゲームやエンターテインメントコンテンツの取引において、従来よりも低コストで迅速な決済を実現することの意義は大きい。金融とコンテンツ事業の融合による差別化戦略は、他の金融機関には真似しづらい独自性を持っていると言えよう。
【次ページ】みんな、北國、JPYCなど日本勢の「事業戦略」と米国の「財政戦略」
ステーブルコインのおすすめコンテンツ
ステーブルコインの関連コンテンツ
PR
PR
PR