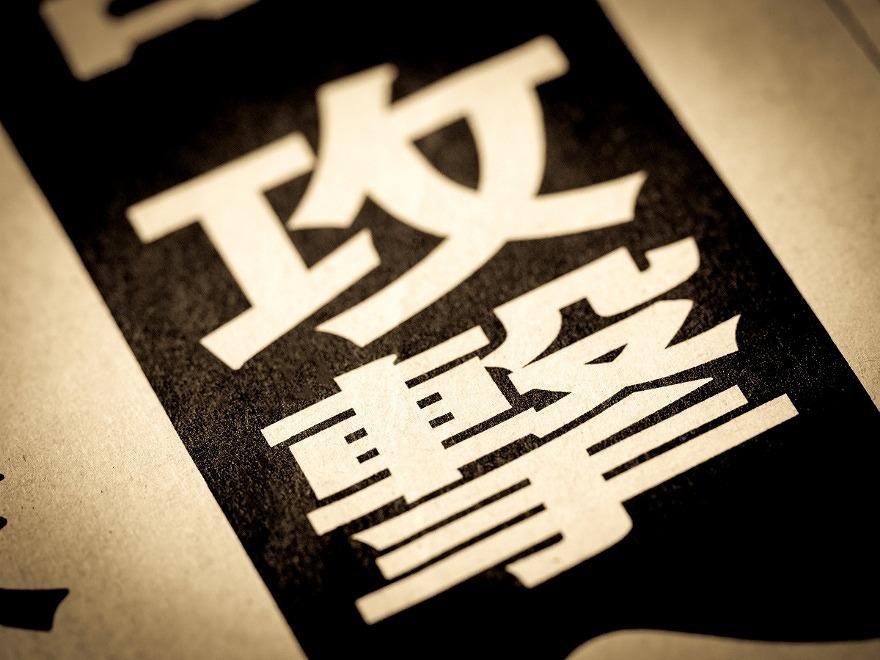- 会員限定
- 2025/11/20 掲載
新潟・柏崎刈羽原発に行ってわかった「現場のリアルな苦労」と「再稼働しないリスク」
連載:小倉健一の最新ビジネストレンド
1979年生まれ。京都大学経済学部卒業。国会議員秘書を経てプレジデント社へ入社、プレジデント編集部配属。経済誌としては当時最年少でプレジデント編集長。現在、イトモス研究所所長。著書に『週刊誌がなくなる日』など。
日本のエネ政策の「奇妙な問題」
先日、あるニュースが筆者の目に留まった。原子力関連団体の原子力エネルギー協議会(ATENA)が、テロ対策施設の設置期限を延長してほしい、と原子力規制委員会に要望を出したというのだ。理由は、建設業界の労働環境改善に伴う工期の長期化だという。一見すると、単なる業界の都合にも見えるこのニュースの裏側に、実は日本のエネルギー政策を巡る、より根深く奇妙な問題が隠されている。
この「テロ対策」とは、一体何なのか。その中心にあるのが、「大型旅客機が意図的に原発へと突っ込んでくる自爆テロ」への備えである。これは、特定重大事故等対処施設、通称「特重施設」に課せられた要件の一部だ。
具体的に言うと、万が一旅客機が原子炉建屋に突っ込んできても、遠隔操作で原子炉を冷却し、破局的な事態を防ぐための堅牢な施設を新たに建設せよ、というものである。この特重施設を含めた、「追加的安全対策費」と呼ばれるコストは1基あたり数千億円にものぼる。安全を追求する姿勢はもちろん重要だが、このあまりにも莫大な金額が果たして現実的なリスクから乖離(かいり)していないのかは、疑問の余地が残る。
原発に「旅客機が墜落」は本当にあり得るのか
このことを考える上では、まずそのシナリオの蓋然性について冷静に問わなければならない。なぜ、テロリストは世界の政治・経済の中枢であり、絶大なシンボル的価値を持つ東京や大阪ではなく、周辺の人口も少なく、突撃する標的としても小さく狙いづらい原子力発電所をピンポイントで狙うのか。テロリズムが単なる破壊活動ではなく、政治的なメッセージを伴うパフォーマンスである以上、その標的選択には合理性が伴うはずだ。原子力発電所を狙う動機が、論理的に説明できるだろうか。さらに疑問なのは、手段としての非効率性である。米国同時多発テロによりセキュリティ対策が強化された現在、テロの主役は、20年以上前にニューヨークの空で目撃されたような大型旅客機ではなくなってきていると見受けられる。実際、英オックスフォード大の研究者らの協力によって運営されている統計サイト「Our World in Data」のデータを見ると、旅客機のハイジャックは1970~80年代に頻発し、2001年の9.11以降は大きく減少している。
こうした現状を見ると、2001年の米国同時多発テロ時点の考え方からアップデートされないまま、「旅客機の衝突」という現在ではリスクが低い脅威への対策に重きを置き続けているように見えてしまう。
リスクの大きさと発生確率を掛け合わせて合理的に優先順位を付けるという、「当たり前」の判断が欠落した結果、巨額のコストと時間が蓋然性の低いリスク対策に費やされていく。もちろん、安全が第一なのは言うまでもない。ただ、電力政策において、非効率とも言えるこのような点は、一度冷静に検証や見直しがされるべきでないだろうか。 【次ページ】【凸ってみた】原発に行ってわかった「現場の苦労」
エネルギー・電力のおすすめコンテンツ
PR
PR
PR