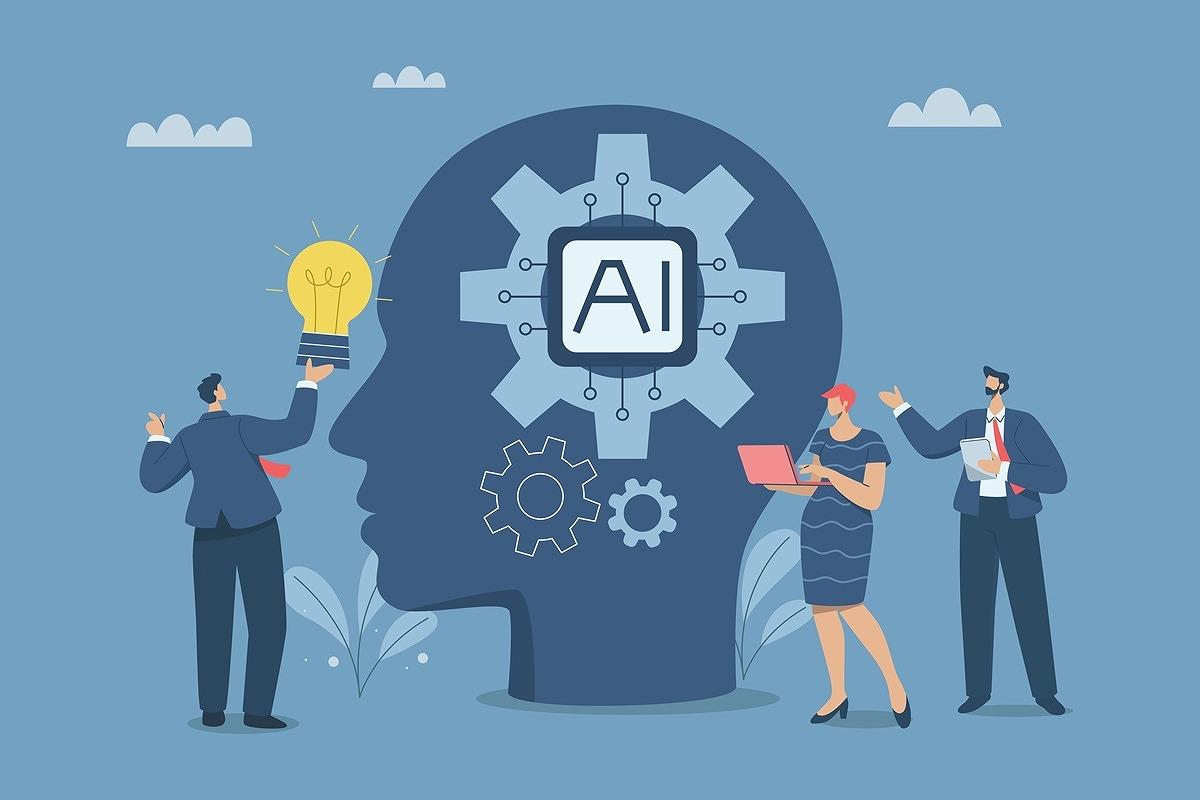- 会員限定
- 2025/11/03 掲載
生成AIで激変「中間管理職」のまったく新しい役割とは、組織の意思決定はどう変わる?
連載:野口悠紀雄のデジタルイノベーションの本質
1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任。一橋大学名誉教授。
noteアカウント:https://note.com/yukionoguchi
Xアカウント:@yukionoguchi10
野口ホームページ:https://www.noguchi.co.jp/
★本連載が書籍化されました★
『どうすれば日本経済は復活できるのか』 著者:野口悠紀雄
購入サイトはこちら:https://www.sbcr.jp/product/4815610104/
集合知の形成とは“たとえば”何か?
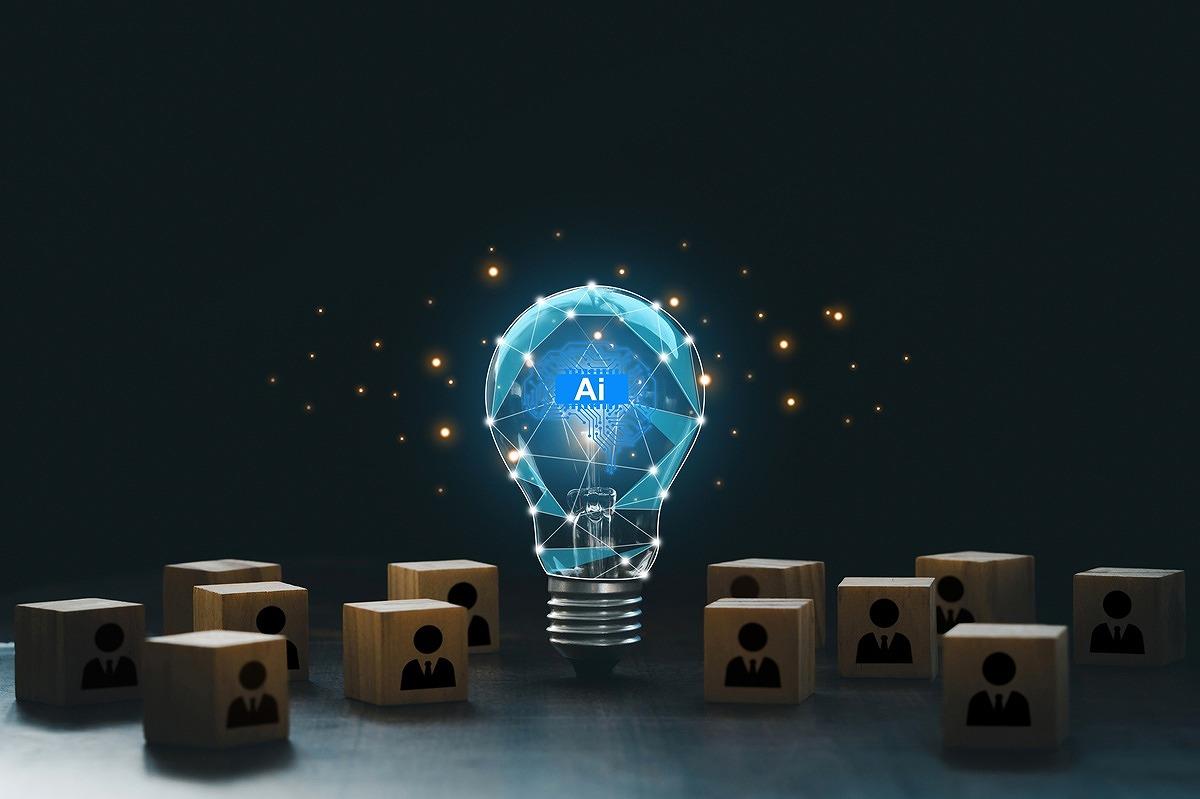
たとえば、コールセンターの顧客応対ログを生成AIで要約・分類し、よくある問い合わせやクレーム内容のパターンを自動抽出することで、新商品開発や従業員教育に役立てることができる。これは生成AIが単なる情報処理ツールではなく、「知識の意味づけと再利用」を可能にする装置として機能し得ることを示している。
また複数部門の報告書やトラブル対応記録をAIで横断的に分析すれば、各部門ではさほど問題視されていない事象が、全社的には見過ごせないレベルに達していることが分かるかもしれない。
集合知の重要性はかねてから指摘されていたが、それを形成・実現していくための手段が不十分であったため、現実化することは稀であった。現在では、生成AIという強力な手段が利用可能になり、集合知の形成と利用が現実的な課題となった。 【次ページ】「生成AIで集合知形成」と「AIエージェント」の決定的な違い
AI・生成AIのおすすめコンテンツ
AI・生成AIの関連コンテンツ
PR
PR
PR