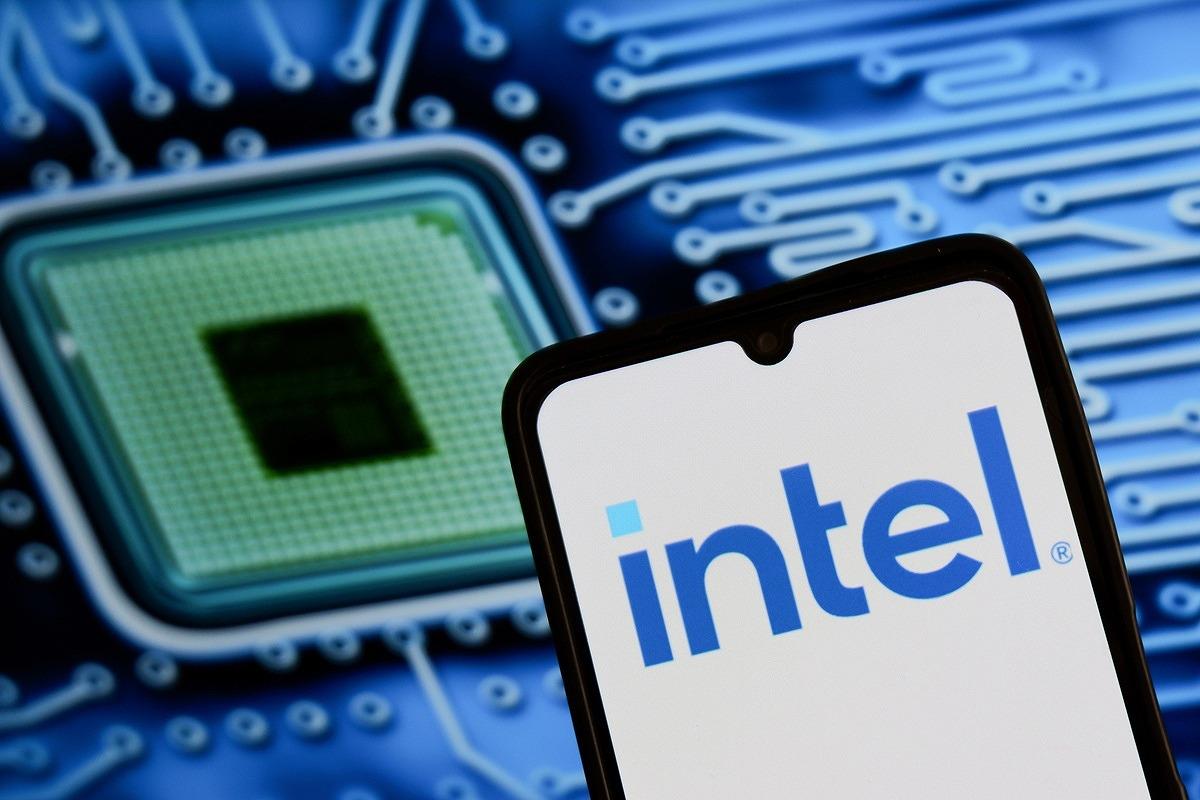- 会員限定
- 2025/09/17 掲載
なぜ米政府が「インテル筆頭株主」に? 国有化もあり得る「崖っぷちの裏事情」とは
連載:米国の動向から読み解くビジネス羅針盤
米NBCニュースの東京総局、読売新聞の英字新聞部、日経国際ニュースセンターなどで金融・経済報道の基礎を学ぶ。現在、米国の経済を広く深く分析した記事を『週刊エコノミスト』などの紙媒体に発表する一方、『Japan In-Depth』や『ZUU Online』など多チャンネルで配信されるウェブメディアにも寄稿する。海外大物の長時間インタビューも手掛けており、金融・マクロ経済・エネルギー・企業分析などの記事執筆と翻訳が得意分野。国際政治をはじめ、子育て・教育・司法・犯罪など社会の分析も幅広く提供する。「時代の流れを一歩先取りする分析」を心掛ける。
米政府が「インテルの筆頭株主」に
トランプ政権は8月、インテルと投資合意を締結した。米国内の半導体製造能力を強化して経済安全保障を確保するため、バイデン前政権下で制定されたCHIPSプラス法(CHIPS and Science Act)に基づき、株式との交換なしでインテルに交付されるはずだった連邦政府補助金の性格を変更するものだ。米政府が同社株式の9.9%に相当する4億3330万株を保有し、筆頭株主に躍り出た。米政府の出資の原資は、未支給分の補助金57億ドルに加えて、国防総省と商務省が共同で推進する「機密データ保護機能付きの半導体製造支援プログラム」で支給が予定されていた補助金32億ドルだ。
政府保有株式は「パッシブ投資」で、原則として取締役会への参加や経営への関与は行わない。だが政府が生産手段を一部支配することで、実質的には経営戦略に介入できるようになり、米産業政策における大転換点となる。
なお、日本のソフトバンクグループが同時に20億ドル(約2,940億円)相当のインテル株式を取得し、同社の6番目に大きい株主となることも発表されている。
今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!
半導体のおすすめコンテンツ
PR
PR
PR