“対応必須”の電帳法&インボイス制度 、「帳票の特性」「デジタル化」で解決する方法とは
- ありがとうございます!
- いいね!した記事一覧をみる
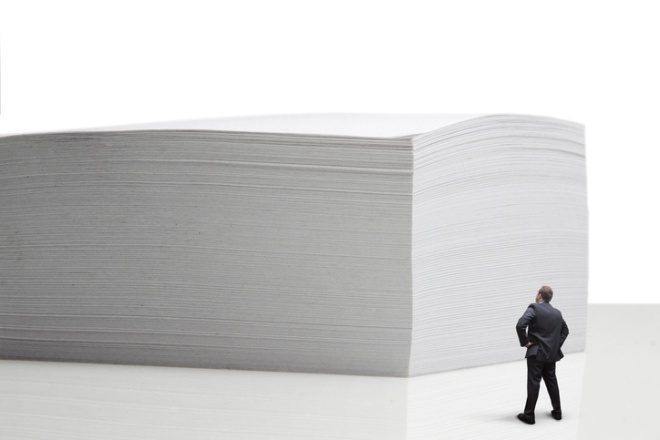
電帳法やインボイス制度への対応を考えれば、2022年は今すぐ動くべき時
「バックオフィスのデジタル化」へのプレッシャーは日に日に増している。国から企業に業務の電子化が求められているためだ。既報のスケジュールから2年の延長はあったものの、2023年には電子帳簿保存法(電帳法)が、同時期にはインボイス制度(請求書に対して、発行事業者番号、適応税率などの情報記載が必要となる。2023年施行予定)への対応も始まる予定だ。現時点でこれまで通り、郵送やFAX、判子について未対応なら、すぐにでも動かないと間に合わない可能性もある。
なぜバックオフィスのデジタル化が進まないのか。理由の1つに、「人の手は使っているが、それでも業務は問題なく回っている。新たな手間や費用をかけてデジタル化するのは面倒」という考えがある。問題がないので変える必要性は低いというわけだ。
しかし紙の資料で業務をするには保管や管理が必要であり、ファイリングする工数や、保管場所などのコスト負担は必須である。監査の際にも、書類を探すのが困難になったり、過去の書類をすぐに発見できなかったりと、利便性の低さは否定できない。
では、どうするべきか? 法制度への対応だけでなく、日本企業が利用している帳票の特性を考慮しつつ、バックオフィス業務のデジタル化を実現する方法がある。鍵となるのは「企業間のあらゆる文書をデータ化すること」だった──。
今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!

