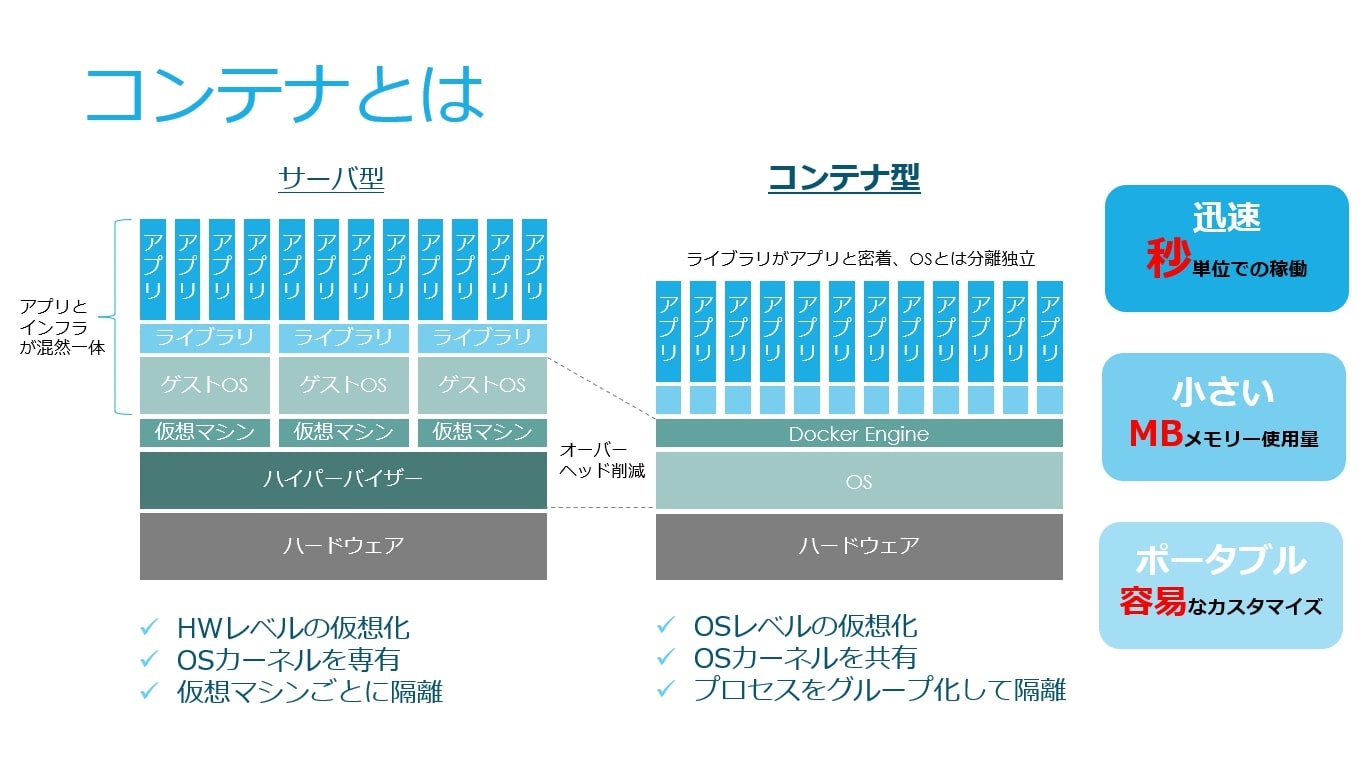今さら聞けない「コンテナ」基礎知識。Docker、Kubernetesは?OpenShiftの活用法も
- ありがとうございます!
- いいね!した記事一覧をみる

「コンテナ」は、アプリとインフラを分離させた画期的な技術
1960年代のメインフレームから始まったコンピュータの歴史では、OSとアプリケーションは常にサーバという枠の中で動いていた。サーバ仮想化においても、サーバという枠組みそのものが仮想化されただけで、その基本構造は変わらなかった。それが「コンテナ」の登場で大きく変わった。数十年のコンピュータの歴史の中で、初めてアプリケーションとインフラが分離するという、画期的な出来事が起きたのである。
従来のサーバ型の仕組みでは、アプリケーションが稼働するには、OSと一体化したライブラリを利用する必要があった。一方のコンテナでは、オープンソースソフトウェア(OSS)である「Docker」によりライブラリはOSから切り離され、アプリケーションと一体化している。ライブラリと一体化したアプリケーションは「コンテナ」という単位でプロセスとして動く。このため、起動が非常に高速で、メモリ使用量も小さく、Dockerが動いていればOSのバージョンが異なっても稼働する。
コンテナによって、開発者はOS以下のインフラから解放され、さまざまな開発用ツールを瞬時に起動し、バージョンの異なるアプリケーションを併存させて開発可能になった。
- ・開発者の世界にとどまらないコンテナの可能性
- ・「Kubernetes」「OpenShift」が必要になった背景
- ・KubernetesとOpenShift、その違いは?
- ・OpenShift導入・構築のポイントはネットワーク
- ・コンテナ導入により従来の運用見直しも不可欠
今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!