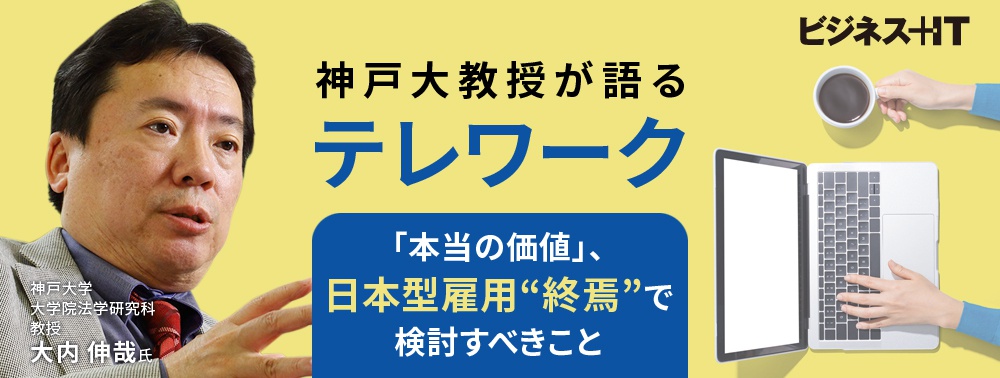- ありがとうございます!
- いいね!した記事一覧をみる
神戸大教授が語るテレワーク「本当の価値」、日本型雇用“終焉”で検討すべきこと
総務省の発表によると、2021年9月時点でテレワークを導入した企業は5割を超えた。新型コロナの感染防止策として導入を始めた企業が多いが、テレワークはDX(デジタルトランスフォーメーション)時代にフィットした働き方であり、今後は主流になるとも考えられている。しかし、新しい働き方のため、既存の法制度や人事制度と衝突する点もある。企業や政府は何を課題として捉え、検討していけばよいのか。神戸大学大学院法学研究科教授 大内 伸哉 氏に聞いた。働き方の主流となるテレワーク
「今後、テレワークが働き方の主流になると思っています」と語るのは、神戸大学大学院法学研究科教授 大内 伸哉 氏だ。雇用社会が大きく変わるなかで、学生に労働法を教える大内氏。研究しているのは、今後どのような雇用社会になり、政策的な課題としてどのようなものが挙げられ、どのような法的ルールが必要となるのかということだ。
「テレワークが働き方の主流になる理由の一つが、ICT(情報通信技術)の発達です」(大内氏)
ICTの発達により、テレワークに必要なオンラインによる情報のやり取りがしやすくなった。今後も5Gなどの通信規格の発展によりテレワークを支える技術環境は一層整備されるだろう。
「もちろん、技術の進化だけが、テレワークが働き方の主流になると考える理由ではありません。テレワークにはメリットが多いということも挙げられます」(大内氏)
以下では「企業」「労働者」「社会」それぞれの側面におけるテレワークの真の価値、そして企業が検討しなければならない論点や課題について解説する。
今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
-
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
-
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
-
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
-
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!