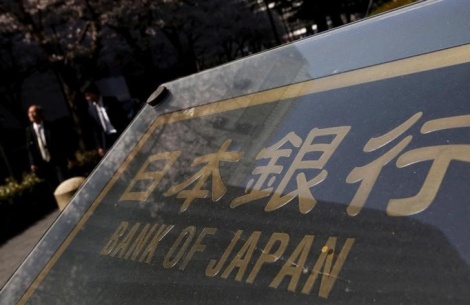- 2023/02/13 掲載
アングル:日銀新総裁、透ける市場と安倍派への配慮 政府案あす提示
<岸田政権に届いた反対意見>
「今の政策を継続しながら、その中で改革が必要。新メンバーに前向きな取り組みを期待したい」。自民党の萩生田光一政調会長は12日のNHK番組で、近く提示される人事案について「コメントは控える」と断ったうえで、一定の理解を示した。
総裁ポストは旧大蔵省を含め、財務省と日銀出身者のたすき掛け人事が一部の例外を除いて続いてきた。植田氏が承認されれば戦後初めて学者を起用することになる。政府は14日に国会へ人事案を提示し、24日に衆議院、27日に参議院で所信聴取を行う。
政府関係者の間では「引き締め的な金融政策を支持するタカ派でも、緩和的な政策を支持するハト派でもなくバランスがいい。良い人選だった」(財務省関係者)との声が出ている。
日銀幹部は「調節なども含めた実務の知識も大事にしながらきちんと政策を筋道立てて考えて説明できる」と植田氏を評価。副総裁への起用が固まった氷見野良三前金融庁長官については「金融規制に関する国際的なプレゼンスが大きい」、内田真一日銀理事については「行内のこともよくわかった上で組織運営も含めて落とし込んでいく役割が期待される」と話す。
4月に任期を迎える財務省出身の黒田総裁の後任人事を巡っては、日銀プロパーの雨宮正佳副総裁と中曽宏・前副総裁の名前が有力候補として浮上していた。特に金融政策を立案する企画畑を歩み、黒田総裁の下で理事、副総裁を務めた雨宮氏が本命との見方が市場関係者の間やメディアで広がっていた。
2013年4月に発足した黒田体制は、国債の大量購入に始まり、マイナス金利、長短金利操作(YCC)と新たな手段を次々と導入した。当初は株高に沸いたものの、インフレ高進で各国中央銀行が利上げに動く今、日本の金利にも上昇圧力がかかり、急速な円安が物価上昇を招くなど副作用が広がっており、複雑化した金融政策を市場の混乱なく見直せるのは設計者の雨宮氏しかいないとの観測が強まっていた。
だが、複数の関係者によると、岸田政権には早い段階から雨宮氏、中曽氏を次期総裁に充てるのは妥当ではないという意見が届いていた。政府関係者の1人は、「岸田内閣が発足した21年10月直後、一部の日銀OBから、(大規模緩和を進めた)プロパーを推すことに強い反発を受けていた」と話す。
別の政府関係者は「アベノミクスからのイメージを転換するのに、中曽宏・前日銀副総裁、現職の雨宮正佳副総裁ではネックになる。政治的にも、色の付いていない学識者が良かったのでは」と解説する。政府が雨宮氏に総裁就任を打診したと一部で報じられた6日、大規模緩和が続くとの思惑から株が買われ、円は売られた。
日銀OBなど別の関係者らによると、そもそも雨宮氏は周囲に対し、総裁を引き受けることに後ろ向きな発言をしていた。雨宮氏は報道後、メディアの取材に対し、「政府や与党の首脳の方々が事実ではないとおっしゃったと聞いている。それに付け加えることはない」と語った。
<「早期目標」どう対処>
植田氏は1998年から05年まで日銀の審議委員を務めた。ゼロ金利を長期間続けることを約束することで長期金利の低下を促す「時間軸効果」を主導したほか、00年8月のゼロ金利解除では反対票を投じた。
岸田政権が植田氏に白羽の矢を立てた経緯について、与党関係者2人は「安倍派(清和政策研究会)への配慮もあっただろう」と指摘する。総裁人事に先立つ22年3月の日銀審議委員人事で、緩和に積極的な人選を見送ったことで、少なからず「(総裁人事を機に)政策を急転換するのでは」との警戒感があった。
低金利政策からの脱却を急ぎ、経済成長率を超える金利急騰を招けばかえって政府債務を発散させ、子育て予算などへの政策余力が低下しかねない。政権与党内では「拙速な金融引き締めには動けない」(中堅議員)との見方が出ている。
岸田首相は8日の衆院予算委員会で、日銀総裁の資質ついて「主要国の中央銀行トップとの緊密な連携、内外の市場関係者への質の高い発信力と受信力が格段に重要になってきている」と語った。市場にショックを起こさせない一方、黒田緩和を少しずつ修正していく能力と発信力を併せ持った候補者を検討していることをにおわせた。
自身の起用が固まったと一斉に報じられた10日、植田氏は「金融緩和の継続が必要」と都内で記者団に述べた。
植田氏が審議委員だった当時、専属スタッフを務めた野村総研の井上哲也・シニア研究員は「研究スタイルは非常に実証主義的」と表現する。黒田総裁のように劇的な政策を打ち出すことはないとし、物価と賃金の持続的な上昇が確認できれば「データが背中を押す形で日銀の金融政策は正常化すればいいと判断するだろう」と予想する。
経済界では「このまま政策が続けられれば、危機的な事態に陥りかねない」(三菱UFJ銀行の平野信行特別顧問)との声が根強い。平野氏は「異次元緩和で日銀が事実上、国債を買い支えており、国がいくら借金しても大丈夫という意識やばらまき財政支出に歯止めがかけられない」と警鐘を鳴らす。
当面は金融緩和の方向性を維持しつつも、YCCなどの金融緩和を正当化してきた物価安定2%の「早期実現」目標の扱いや、変動許容幅の上限を試す動きにどう対処するかが改めて問われることになる。
13日の東京株式市場は、大規模金融緩和が解除に向かうとの思惑から日経平均は一時前週末比400円以上下げた。
(竹本能文、和田崇彦、杉山健太郎、山口貴也 編集:久保信博)
最新ニュースのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR