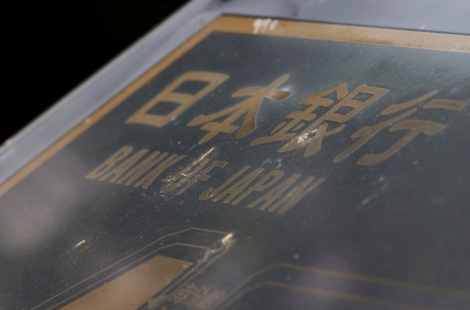- 2022/07/29 掲載
緩和で賃金上昇促し、物価目標目指すのが適当=7月日銀会合主な意見
[東京 29日 ロイター] - 日銀は29日、7月20―21日の金融政策決定会合で出た主な意見を公表した。金融緩和で賃金上昇を促していくことで、物価目標の持続的・安定的な実現を目指していくことが適当など、賃金上昇の実現を重視して金融緩和を継続すべきとの意見が目立った。
一方、新型コロナウイルスの感染急拡大で、9月末に期限を迎えるコロナ対応特別オペの10月以降の取り扱い決定は見送ったものの、「コロナオペは所期の効果を発揮し、役割を終えつつある」との意見が出た。
<需要拡大と賃金上昇へ、「粘り強く緩和を」>
決定会合で取りまとめた「経済・物価情勢の展望」(展望リポート)では、2022年度の消費者物価指数(除く生鮮食品、コアCPI)の政策委員見通しの中央値が前年度比プラス2.3%に引き上げられる一方、実質国内総生産(GDP)の見通し中央値はプラス2.4%に引き下げられた。
ある委員は「日本経済は、感染症からの回復過程にある中で資源高による海外への所得流出という下押し圧力を受けている」と指摘。こうした状況下では「金融緩和によって賃金上昇を促していくことで、物価目標の持続的・安定的な実現を目指していくことが適当だ」と述べた。「需給ギャップは2年以上マイナスであり、需要拡大と持続的な賃金上昇を後押しする現在の金融緩和を粘り強く継続すべきだ」といった意見もあった。
政策運営に当たり、賃金動向の的確な把握が必要との指摘も出された。「企業や家計の予想インフレ率は上昇しているほか、企業の堅調な設備投資計画の背景として期待成長率が上昇している可能性がある」として「企業の将来の売上増加への期待が高まるもとで、賃金上昇が実現する可能性が高まっている」と期待する委員もあった。
一方、ある委員は「現実の物価上昇率だけでなく予想物価上昇率やそれらに基づく先行き見通しを見ながら政策を運営することが適切だ」と指摘した。サービス価格など物価の基調を規定する部分が上昇し、消費者物価上昇率が安定的に2%を超えることが視野に入っていないもとでは、現状の金融緩和を継続することが「当然だ」とする委員もあった。
<10年国債の指し値オペ、「市場機能への影響注視」>
日銀は10年物国債0.25%での指し値オペを連日実施している。決定会合では「名目金利が低位で推移するもとでの最近の予想物価上昇率の高まりは、実質金利の低下を通じて金融緩和効果を強めており、企業の設備投資スタンスの積極化等にもつながっているとみられる」との声が出された。
もっとも、この意見を述べた委員は「金利上昇圧力を抑制するための最近の国債買入れの増加が、国債市場の機能度に与える影響を注視する必要がある」とも述べた。
金融システムは全体として安定性を維持しているものの、「将来どこかの時点で金融緩和の副作用が顕在化し、金融システムに影響するリスクについては、引き続き十分な注意を払っていく必要がある」との意見も見られた。
<米国景気への警戒も>
新型コロナ、ウクライナ情勢、資源価格、海外経済と日本経済を取り巻くリスク要因は多い。会合では「米国が景気後退に陥ったり、国際金融市場に負のショックが生じたりすることで、日本経済に影響が及ぶリスクに注意する必要がある」との指摘が出ていた。
中国での感染再拡大を踏まえ「厳格な公衆衛生上の措置が断続的に導入されることで、世界経済が一段と下押しされるリスクが懸念される」との声も聞かれた。
展望リポートでは「金融・為替市場の動向やその日本経済・物価への影響を十分注視する必要がある」との文言があったが、「主な意見」には為替動向を警戒する意見は記載されなかった。
(和田崇彦 編集:内田慎一)
最新ニュースのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR