- 会員限定
- 2021/10/22 掲載
工藤勇一×坪田信貴:「自ら考えて行動する子」に育てる、たった一つの方法

過剰なサービスが主体性を奪う
「学校教育の課題は、日本社会の課題そのもの」と語るのは、5月に『自律する子の育て方』を上梓した工藤氏だ(本書は神経学者青砥瑞人氏との共著)。大きな課題の一つは「主体性」。日本財団による「18歳意識調査」(2019年11月30日発表)によると、「自分を大人だと思う」と答えた日本の若者は3割弱(中国は約9割、欧米は約8割)。「自分で国や社会を変えられると思う」と答えた若者はわずか約18%、社会課題について、家族や友人など周りの人と積極的に議論している」若者は約27%と、すべての設問に対して日本の若者だけ突出して低い結果となっている。
これらの結果から、日本の若者は当事者意識が決定的に欠如していると総括することができる。ただし、若者だけが受け身思考なわけではなく、日本社会全体が主体性を失っているのだと工藤氏は指摘する。
「現在の新型コロナウイルスへの対策を見ても、政府に何か求めては文句を言う人ばかり。子どもたちの意識は、私たち大人の姿の鏡です」
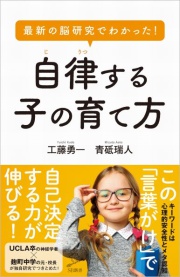
「サービスに慣れた人間は、サービスの質に不満を言うようになり、よりよいサービスを求めます。親や学校があれをしなさい、これをしなさいと指示をするのもサービスの一種。日本の学校教育では、サービスが勝手に与えられるという状態を150年間続けているのです」
メディアでもたびたび取り上げられ、話題となった麹町中学校での取り組みだが、たとえば「担任制の廃止」がある。生徒は進路指導など相談したい先生を指名することができる仕組みに変えた。
担任として生徒を受け持つと、優秀な先生でありたい意識から、サービス提供型になってしまうという構造がある。一方、指名制であれば、教育の本質である「支援」に徹することができる。生徒側も「この先生はハズレだ」などとサービスの質に不満を持つことがなくなる。
これは坪田氏が塾長を務め、「ビリギャル」が学んだ塾としても有名な坪田塾でも同じだ。7月に『「人に迷惑をかけるな」と言ってはいけない』を上梓した坪田氏は「教える授業」をせず、個別にディスカッションをして生徒を支援するが、話し相手となる先生を生徒が選ぶことになっていると説明する。
個別に対話をしつつ、他の先生もチームで生徒を見ていく仕組みなら、先生同士の競争にならず、連携を生む。
当事者意識とメタ認知能力を育てるには
当事者意識というキーワードに関して、坪田氏は「インプットに偏った学習指導では、当事者意識が育たない」と話す。いわゆる大学受験合格を目標にした学習塾ではインプット中心になりそうなものだが、坪田氏が塾長を務める坪田塾ではそうではない。
「たとえば1603年に徳川家康が江戸幕府を開いたという歴史的事実を、ただ覚えるだけでは当事者意識を持ちようがありません。でも、『あなたならどうする? どこに幕府を開く?』などと質問して、リアルに想像してもらうということはできます」
この方法は記憶の面から言っても有効だ。心理学では、いままさにここにあるという感覚=「臨在性」と、自分に関係があるという感覚=「迫真性」があると、記憶に定着すると言われているそうだ。
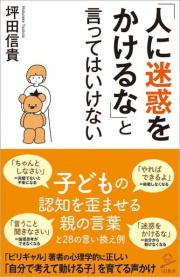
メタ認知とは、自分の状況を俯瞰的に見る力。自ら課題を発見し、自分を成長させることにつながる。社会で活躍できる人は、メタ認知能力が高いというのは、坪田氏、工藤氏両者共通の認識だ。
メタ認知能力は、なかなか自力で身につくものではない。自分を対象化して認知(内省)することを通して高まっていくが、内省は高度な脳機能であると神経学者の青砥瑞人氏が指摘している(『自律する子の育て方』)。子どもたちにメタ認知を学んでもらうには、メタ認知ができる大人が伴走者となって、脳に負荷をかけ続ける必要がある。
「坪田塾では、現状のレベルに合わせて自分で学習します。塾で何をやっているかといえば、テストでアウトプットし、そのアウトプットをベースに先生とディスカッションすること。いまの自分が全体像の中のどこにいて、何をやればいいのかを自分で判断することを繰り返します」
【次ページ】教育を科学的に考える
政府・官公庁・学校教育のおすすめコンテンツ
PR
PR
PR



