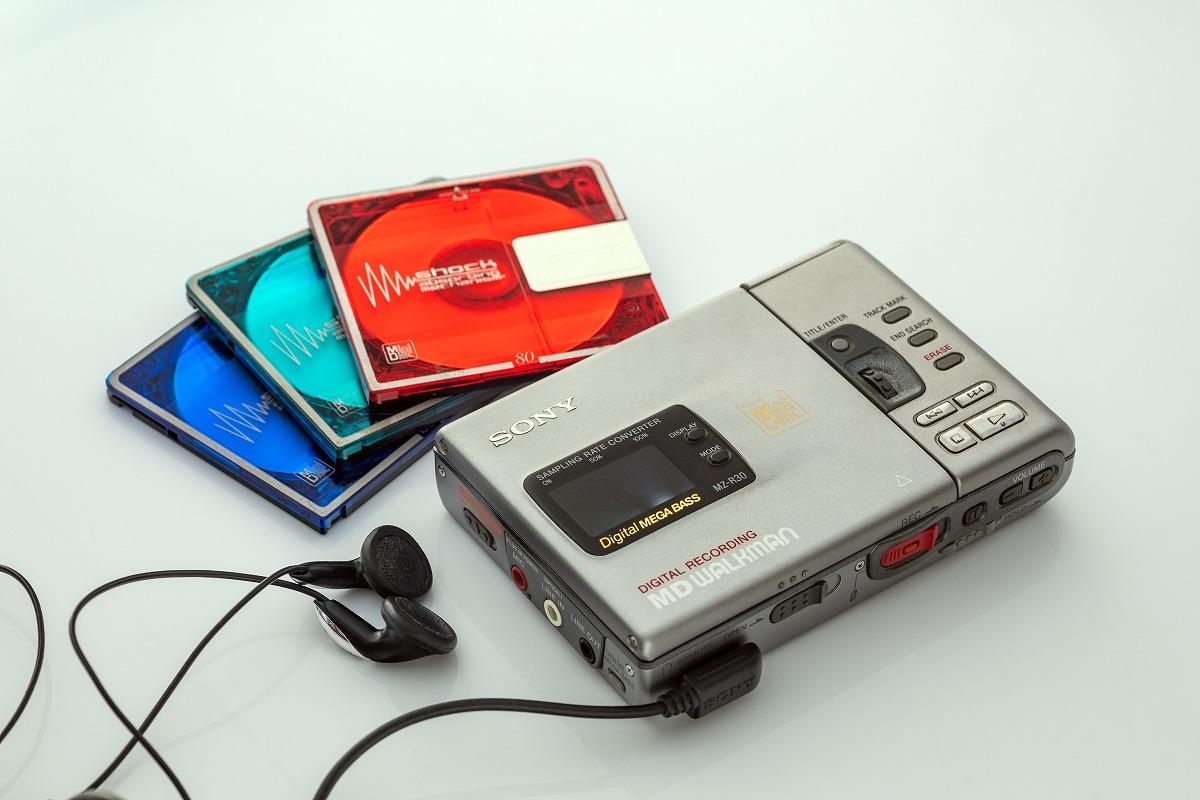- 会員限定
- 2025/07/06 掲載
ソニーの大転換を成功させた、ビジネス視点における「適応」の真実
1983年大阪生まれ。2006年に東京外国語大学英語科を卒業後、外務省入省。2009年米国ペンシルバニア大学で組織開発修士を取得し、外交官としてワシントンDC、イスラエル/パレスチナに駐在。2013年に帰国後は、安全保障や経済問題等さまざまな分野で政府間交渉に携わるかたわら、首相・外相の英語通訳を務める。国益と価値観がぶつかり合う前線に立つ中で、個と組織のあり方に強い関心を持ち、2018年独立。以降、コンサルタントとして国内外の企業の組織・人材開発を支援。リーダーシップ育成、ビジョン・バリュー策定、カルチャー変革、学習型組織作り、事業開発等のサポートを行う。2021年からは米国ミネルバと事業提携し、日本企業向けのリーダーシップ開発プログラム「Managing Complexity」を展開。自身も講師を務める。
生き残り、繁栄するために自らを進化させる「適応」
「適応(Adaptation)」とは、本来さまざまな視点から捉えることができる多面的な概念です。生物学、心理学、社会科学、そしてビジネスの分野で、それぞれ異なる文脈で使われています。共通する核心は「環境の変化に適するために、自らの態様、行動、意識を含め自己を変容させていく営み」であるという点です。私たちが今焦点を当てようとしている組織・リーダーシップ領域を含め、適応とはどのような形で行われるものなのでしょうか。簡単に見ていきましょう。■生物学的視点の適応
生物学において適応とは、種がその生存環境において生き残り、繁栄するために、自らの特性や振る舞いを進化的に発展させる営みを指します。適応の対象には、身体的特徴(例:キリンの長い首)、行動(例:鳥の渡り行動)、または生理的メカニズム(例:砂漠に生息する動物の水分保存能力)が含まれます。ある環境において捕食者から逃れるために速く走れる個体が生き残り、その遺伝子を次世代に伝えることができれば、その種は全体として速く走れる特性を発展させていくことができるようになるわけです。生物学的視点から見る適応には、個そのものの生存戦術というよりは、何世代にもわたる種全体としての繁栄思考が色濃く反映されていると言えるでしょう。
私たちは無意識に「適応」を繰り返している
■心理学的視点の適応心理学では個に焦点を当てます。ここでいう適応とは、個人が社会的、あるいは心理的環境にうまく対処し、自身の健康や幸福を維持するためのプロセスや能力を意味します。とりわけ、ストレスや困難な状況に遭遇した際に、個人がどのようにそれを乗り越え、調整することができるかという点に注目します。
自らその困難を解消しなくてはならないとき、まずは問題自体を解決したり変化させたりする対処法が考えられるでしょう(心理学では「問題中心のコーピング」と呼びます)。仕事に期待されるスピードが早まったとき、業務自体を簡素化したり、あるいは時間管理やタスクの優先順位づけを行ったりすることで、自身にかかる負荷原因そのものを解決することができます。
問題自体に変化を与えることができないときは、「感情中心のコーピング」と呼ばれる手法をとることもあります。大事なプレゼンテーション前に過大な負荷がかかるとき、プレゼン機会自体をなくすことはできないでしょうから、瞑想や深呼吸によってストレス実感を内的に管理しようとするアプローチです。
他者に助けを求めることも心理学的には重要な適応行為です。たとえば職場や家族の問題に直面しているとき、仲の良い友人に打ち明け、話を聞いてもらうといった経験はあなたにもあるのではないでしょうか。このとき、問題自体は解決されないとしても、共感や理解、愛情等を通じて、感情的な負担が軽減されると思います(「情緒的サポート」)。あるいは、有益なアドバイスや情報を得て問題の解決に活用することもあるでしょう(「情報的サポート」)。相談相手によっては、金銭を含む物理的な支援を通じて問題解決への貢献を得られることもあるかと思います(「道具的サポート」)。
このように、心理学的視点で見ると、私たちは日々知らずのうちに適応行為を繰り返しながら自らの健康と幸福を守ろうとしていることがわかります。 【次ページ】ソニーの適応戦略に見る、ビジネス視点の「適応」とは
リーダーシップのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR