- 会員限定
- 2015/05/13 掲載
かつて外資系金融機関の取締役を努めた福原氏が語る、日本のエリートは哲学を学ぶべき
「考える力」を磨く 世界のエリートは、哲学ベースの行動原理で動いている

福原 正大氏
──ご自身にとって、哲学とはどういう位置づけしょうか? 哲学にはどんなメリットがありますか?
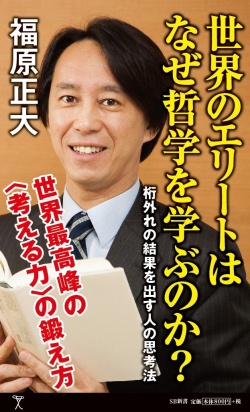
ですから、順風満帆のときには哲学はいりません。むしろ何か仕事に失敗したり、大切な友人をなくしたり、窮地に陥ったときに生きる因(よすが)となるものでしょう。いろいろなことに深刻に悩んでしまう人ほど、ロジカルな哲学が役立つかもしれません。ショーペンハウアー(注1)にしても、哲学者は本当にボロボロな人ばかりですよね(笑)。それでも人間は何とかなるということです。
これまで個人的に多くの哲学書を読んできましたが、やはり高校時代に初めて触れた「人生は使い方を知れば長い」という、セネカ(注2)の『人生の短さについて』という一編に最も影響を受けました。とにかく失敗してもよいので、自分が考えたことを実行していくという感覚をセネカから学びました。
注1:アルトゥル・ショーペンハウアー(1788年-1860年):ドイツの哲学者。仏教精神とインド哲学の精髄を語り尽くした思想家。ニーチェなど多くの哲学者、芸術家、作家に重要な影響を与えた、実存主義の先駆者とも言われている。
注2:ルキウス・アンナエウス・セネカ(紀元前1年頃-65年):ローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。皇帝ネロの幼少期に家庭教師を務め、治世初期にはブレーンとして支えた。ストア派の哲学者であり、多くの著作を有するラテン文学白銀期を代表する人物。
──金融のプロとして第一線で活躍されていた福原さんの根っこに、実は哲学があったというのは面白いですね。
福原氏:世の中には優秀な人が多いので、それならば自分は皆と違う道を選ぼう、ということを考えました。正直に言うと、私は自分が能力的にエリートだと思ったことは一度もありません。ただし、英語ではなくフランス語に没頭するなど、人と違う道を歩むタイプで、それに長けていたと思います。掛け算でいうと、フランス語×英語×哲学×金融×外資というように、全部を掛け合わせると対抗馬がいないくなるように人生のキャリアを積んできたのです。
また、人間は努力すれば何とかなる。そう感じ始めたのが、東京銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に入行してから2年目ぐらいです。世界トップ3に位置づけられる欧州経営大学院、INSEADに留学できたのですが、ここには世界中から選りすぐりの人々が集い、競い合っていました。自分は英語が得意ではなかったので、グループワークでさぼり気味だったのですが、そのとき仲間に「お前は逃げているだけだ」と指摘されました。「英語ができないのなら、せめて中身の勉強を100倍してこい。英語が話せないだけでなく、話す中身さえないじゃないか」と。
そこで自分の甘さに気づき、そのころから発奮して、がむしゃらに勉強するようになり、その後は成績もどんどん向上していきました。INSEADを卒業した後、エリート教育の代名詞として知られるフランス・グランゼコールの商業系の最高峰HECに進み、そこで最優秀賞(mention: Très Bien)で卒業できたのも、INSEADで苦しんだ体験のおかげです。
また30歳のときに、世界最大級の資産運用会社であるバークレイズ・グローバル・インベスターズに入社しました。もちろん社員は全員が優秀な方々ばかりです。そこで私は最高のリーダーに出会い、彼の下でいろいろなことを学びました。ここでも人と違う部分で勝負することで、一番下のアソシエートから、最短の5年でトップのマネージメントダイレクターに昇格し、全体をみることができるようになりました。
──著書に「自分は無知である」と知るのが重要とあります。
福原氏:まず、自分が何でも知っていると思うことは大きな勘違いだと思います。たとえば、死について怖いという人がいます。しかし、誰も死ぬまで死を経験することはありません。死に至る過程は怖いかもしれませんが、ソクラテスの弁明では「無知の知」から、人間の生死に関わる深い洞察を導き出しています。「死は人間にとって最大の幸福であるかもしれない。夢一つさえ見ないほど熟睡した状態、まったくの虚無に帰ることを意味するものかもしれない」ということです。
人が無知なのは当然のことで、実は真理が何であるかも分かりません。自然科学ですら「反証可能性がある中で、いまだに反証されていないことを真理と考える」というカール・ポパー(注3)の考え方に基づいています。科学理論は、あくまで論理的な推論に基づく演繹的な仮説の総体でしかありません。自然科学のように、真理に近いと考えられる解がない根源的なテーマを哲学では扱っています。簡単に解決できない問題について自問自答するのが哲学なのです。この問いかけこそが「考える力」を磨く最高のトレーニングになるわけです。
注3:カール・ポパー(1902年-1994年):反証可能性を基軸とする科学的方法を提唱したイギリスの哲学者。科学理論は、論理的推論に基づく演繹的な仮説の総体で、科学はそれを実験で反証する。科学は基本的に間違い探しであり、絶対的な真理を探求しているわけではない。反証可能性がない理論は、真理と無関係に科学的仮説から除外される。
【次ページ】 日本のエリートと欧米のエリートは何が違うのか
人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR


