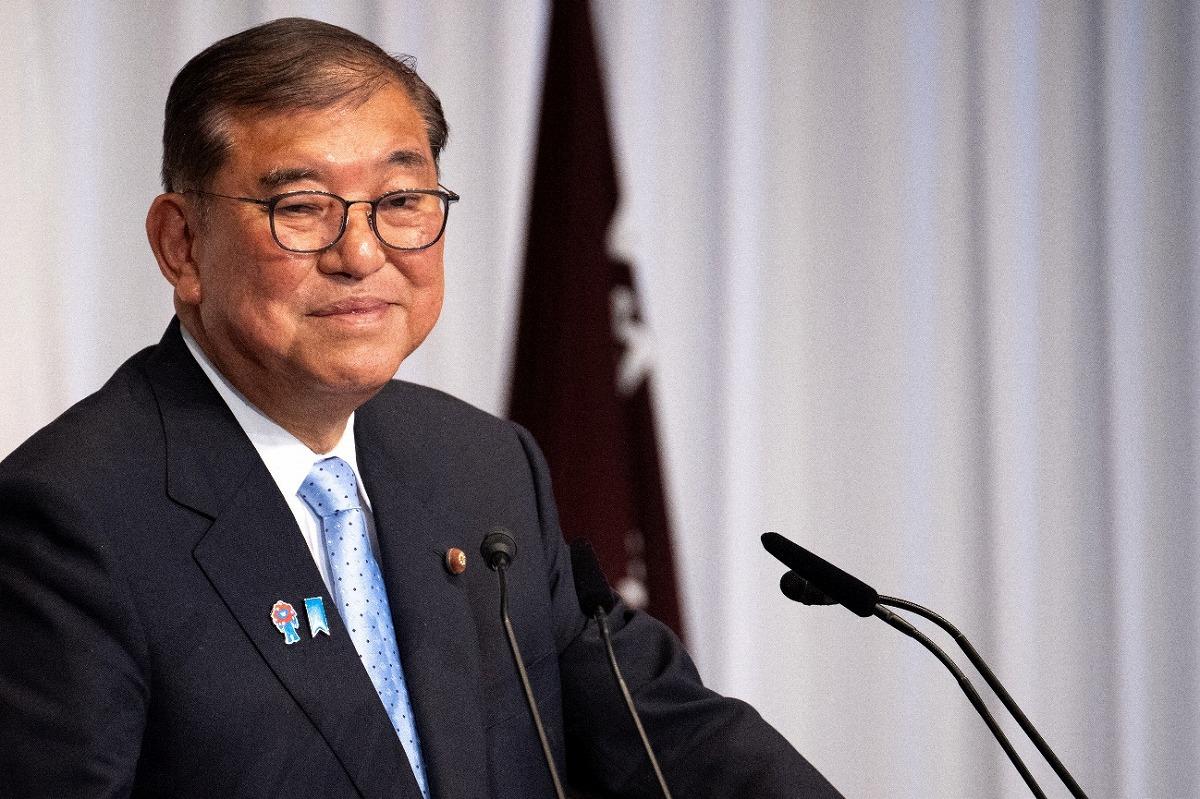- 会員限定
- 2025/07/25 掲載
国民民主か参政か「自公から政権交代」3つの具体シナリオ「居座り石破を見限った」
連載:小倉健一の最新ビジネストレンド
1979年生まれ。京都大学経済学部卒業。国会議員秘書を経てプレジデント社へ入社、プレジデント編集部配属。経済誌としては当時最年少でプレジデント編集長。現在、イトモス研究所所長。著書に『週刊誌がなくなる日』など。
自民党が「歴史的な後退」に陥ったワケ
7月20日に投開票された参議院選挙は、日本の政治地図を大きく塗り替える結果となった。国民民主党と参政党が共に躍進し、既存の政治勢力に揺さぶりをかけた。国民民主党は比例代表で約762万票を獲得、参政党も約742万票を集め、両党は野党第一党であった立憲民主党の約739万票を上回った。自由民主党は約1208万票にとどまり、前回選挙から約545万票も失う歴史的な後退を経験した。石破首相の不人気ぶりは際立っており、大敗でも居座りを表明する石破首相をもはや見限ったといっていいだろう。
ただ、この躍進の背景には、国民民主党の玉木雄一郎代表と参政党の神谷宗幣代表が展開した訴えがあったことも忘れてはならない。両代表は、バブル経済崩壊後の「失われた30年」の責任は長期政権を担ってきた自由民主党と公明党にあると断じ、経済政策の抜本的な転換を共通して主張した。
玉木代表は所得税減税による手取り増加を、神谷代表は減税と積極財政への転換を訴え、多くの有権者の共感を獲得。両党は、政府が物価高対策として打ち出した給付金政策を対症療法に過ぎないと批判し、恒久的な減税こそが国民生活を豊かにする道であると力説した。
今回の参議院選挙の投票率が58.51%と前回から6.46ポイント上昇した背景には、両代表の演説に触発され、普段、選挙へ行かない層が投票した影響も無視できない。玉木代表は有権者の行動が政治を変えると訴え、神谷代表は「投票率80%」という具体的な目標を掲げ、政治参加を促した。
国民民主党と参政党の訴えは何が違うのか?
演説内容には明確な相違点も存在した。玉木代表が演説時間の大部分を経済政策の説明に費やしたのに対し、神谷代表は経済問題に加え、選択的夫婦別姓への反対、外国人労働者問題、グローバリズムへの懐疑といった、より広範なテーマに言及した。玉木代表の戦略は、保守やリベラルといったイデオロギーの垣根を越え、現政権に不満を持つ幅広い層の支持を集めることを目的としていたと見られる。
神谷代表の戦略は、経済政策の転換を求める層に加え、石破政権下で自由民主党から離れた保守層の受け皿となることを明確に意識したものであった。両党の戦略は成功し、自由民主党や立憲民主党に失望した有権者の票の多くを吸収した。
この結果を受け、国民民主党の玉木代表は、立憲民主党との選挙協力に見切りをつける考えを表明した。
玉木代表は記者会見で「自民党への不満を受け止めるには、旧民主党系はもう限界だ」「参政党が立派なのは、全国に候補者を立てたことだ」と述べ、次期衆議院選挙では全国の選挙区に候補者を積極的に擁立する方針を打ち出した。
過去の選挙において、国民民主党は立憲民主党に配慮し、多くの選挙区で候補者擁立を見送ってきた。今回の参議院選挙でも、立憲民主党の公認候補が存在し国民民主党の候補者がいなかった選挙区は18にのぼる一方、逆のケースはわずか9選挙区であった。
このような不平等な協力関係を強いられながら、比例代表で立憲民主党を上回る票を獲得したという事実が、国民民主党の自信となり、単独路線への舵を切る大きな要因となった。
新勢力がさらに躍進するための「ジレンマ」
国民民主党と参政党がそれぞれ全選挙区に候補者を擁立する戦略は、両党が全国政党として飛躍するための重要なステップである。選挙区に候補者を立てることは、党の知名度を向上させ、比例代表の得票を伸ばす上で極めて有効な手段だ。しかし、この戦略は大きなジレンマを内包する。
両党が同じ選挙区で競合すれば、自由民主党・公明党政権への批判票が分散し、結果として与党候補を利する「共倒れ」のリスクが高まるからだ。
参議院選挙の群馬選挙区の結果は、この危険性を象徴している。群馬選挙区では自由民主党候補が当選し、参政党候補が約2万8000票差の次点で敗れた。立憲民主党候補は参政党候補からさらに10万票近く離された3番手であった。
仮に野党候補が一本化されていれば、自由民主党候補に勝利できた可能性を否定できない。国民民主党と参政党が、それぞれ支持を拡大しながらも、お互いに票を奪い合う構図が続けば、政権交代は遠のいてしまう。 【次ページ】国民民主党や参政党が「政権奪取」する具体的な3つの方法
政府・官公庁・学校教育のおすすめコンテンツ
PR
PR
PR