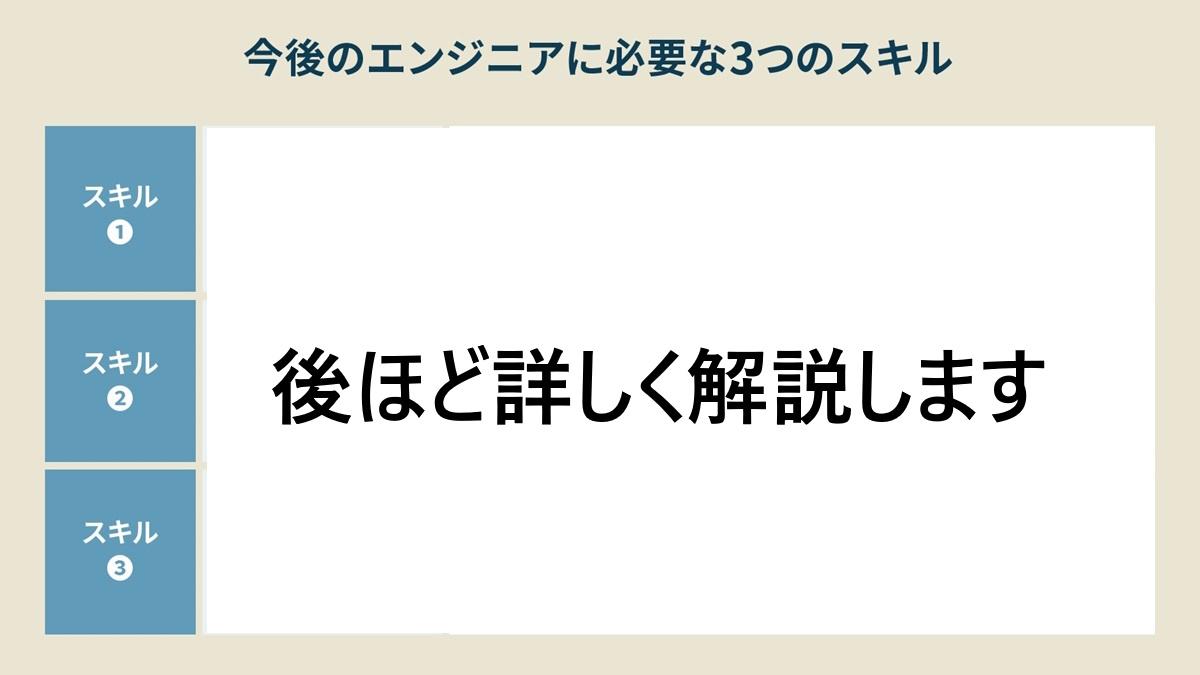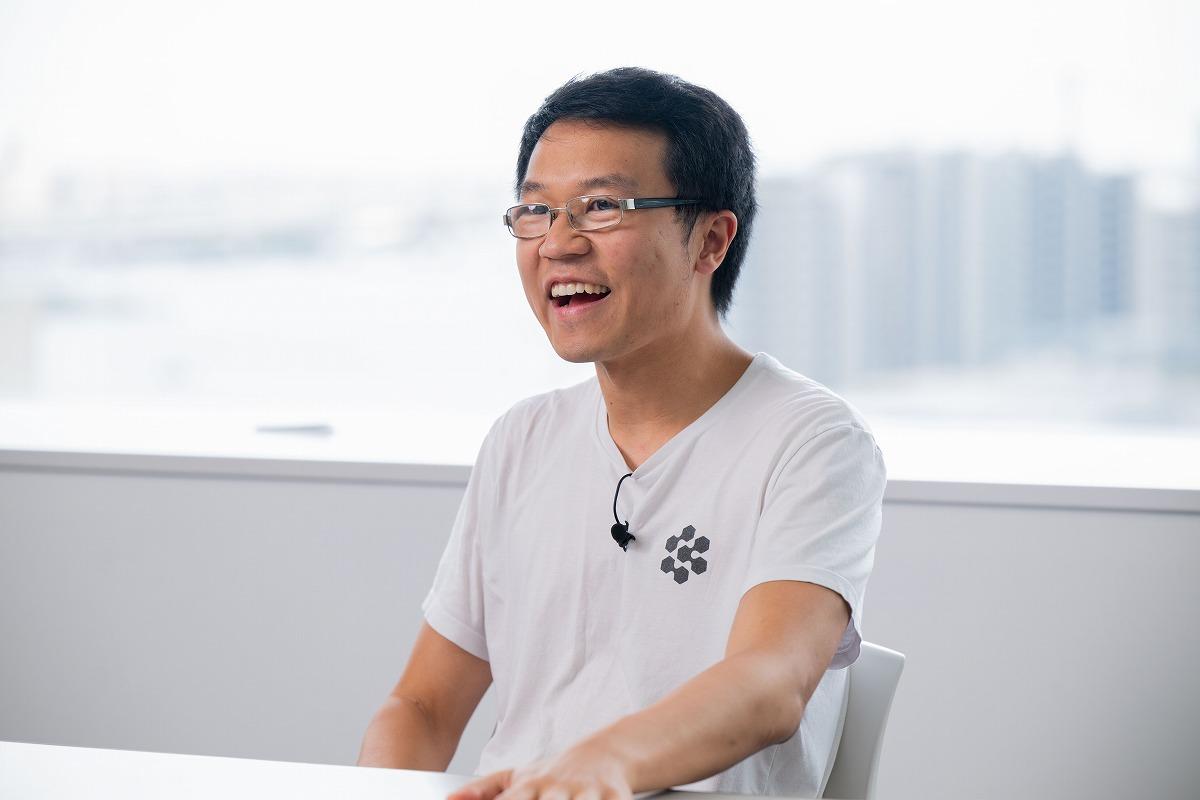- 会員限定
- 2025/10/07 掲載
エンジニア不要論に異議! Devin開発者に聞いた、AI時代に絶対必須の「3スキル」
1993年早稲田大学第一文学部卒業後、ぎょうせい入社。地方行政をテーマとした月刊誌の編集者として、IT政策や産業振興、防災、技術開発、まちおこし、医療/福祉などのテーマを中心に携わる。2001年に日本能率協会マネジメントセンター入社。国際経済や生産技術、人材育成、電子政府・自治体などをテーマとした書籍やムックを企画・編集。2004年、IDG Japan入社。月刊「CIO Magazine」の編集者として、企業の経営とITとの連携を主眼に活動。リスクマネジメント、コンプライアンス、セキュリティ、クラウドコンピューティング等をテーマに、紙媒体とWeb、イベントを複合した企画を数多く展開。2007年より同誌副編集長。2010年8月、タマク設立、代表取締役に就任。エンタープライズIT、地方行政、企業経営、流通業、医療などを中心フィールドに、出版媒体やインターネット媒体等での執筆/編集/企画を行っている。
前編はこちら(この記事は後編です)
現実となった「10倍の生産性向上」
私たちが開発したDevinは、大きく活用が進んでいます。そうした中で、私たちが特に注目しているのは「生産性の飛躍的な向上」です。ブラジルのフィンテック企業であるNubank(ヌーバンク)のユースケース(詳しくは前編参照)において、特定のプロジェクトの作業速度が8~12倍に達しました。つまり、エンジニアがDevinを使って1時間でこなした作業は、従来のやり方であれば8~12時間かかっていた、ということです。
もちろん、こうした劇的な成果は、すべてのケースで実現できるわけではありません。今のところ、ごく特定の条件において発揮されるものであることも事実です。しかし、私たちはこの生産性向上の可能性を、より幅広い領域に拡大していきたいと考えています。
将来的には、すべてのエンジニアがこれまでの「10倍の数のソフトウェア」を生み出せる世界を目指しているのです。それは決してすぐに実現できるものではありませんが、確実に近づいている未来だと信じています。
人間のエンジニアは「不要」になるのか?
AIによる自動化が進む一方、「いずれ人間のエンジニアは不要になるのではないか」といった声を耳にします。しかし、私はそうは思いません。コンピューターやAIがいかに強力な存在になったとしても、「何を作るのか」を決める役割はこれからも人間にしか担えないと考えているからです。そしてこの「何を作るかを決める」という行為には、非常に高度なスキルが求められます。自分が下す判断の1つひとつを理解し、何を構築しようとしているのかを深く把握しなければなりません。
まさにそれこそが、ソフトウェアエンジニアリングの本質だと思っています。つまり、「何を作るべきかを決めること」自体が、ソフトウェアエンジニアリングなのです。 【次ページ】プログラミングで「変わったこと」「変わらなかったこと」
AI・生成AIのおすすめコンテンツ
AI・生成AIの関連コンテンツ
PR
PR
PR