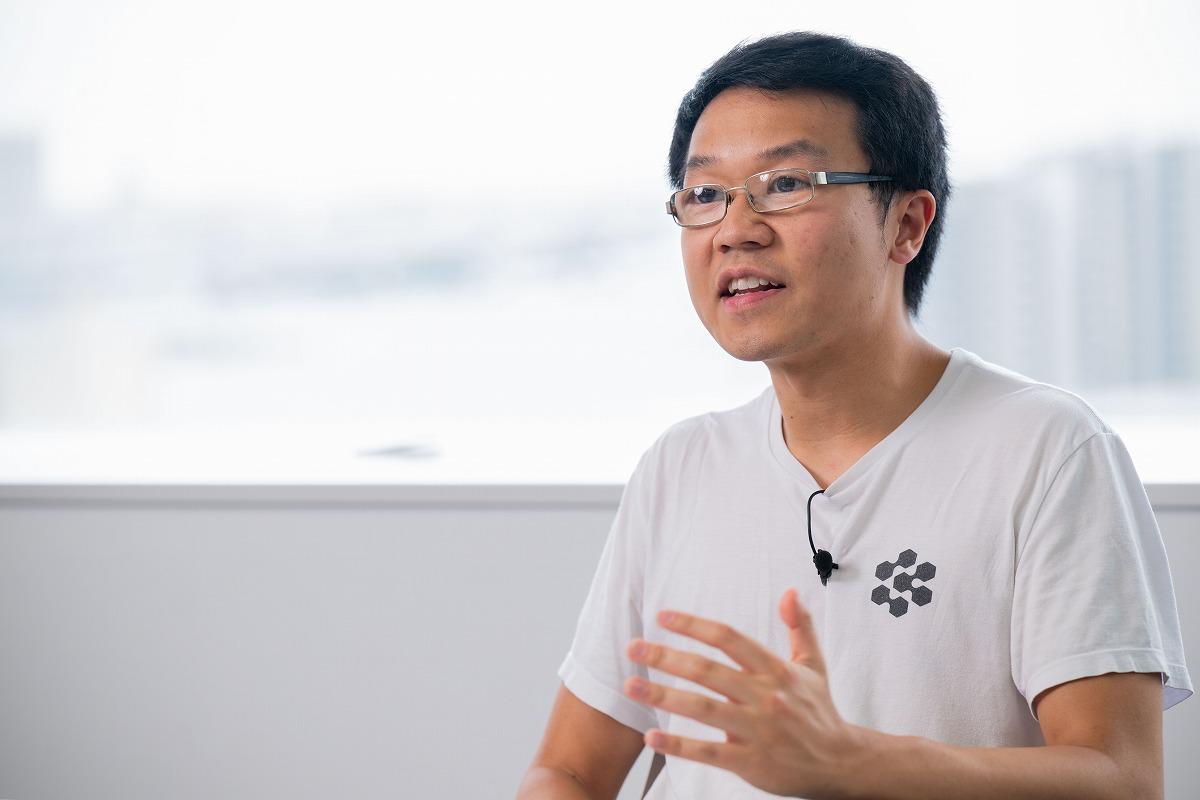- 会員限定
- 2025/09/30 掲載
【完全版】あまりに凄い「Devin」の実力、CEOに聞いた「開発AIエージェント」の正体
1993年早稲田大学第一文学部卒業後、ぎょうせい入社。地方行政をテーマとした月刊誌の編集者として、IT政策や産業振興、防災、技術開発、まちおこし、医療/福祉などのテーマを中心に携わる。2001年に日本能率協会マネジメントセンター入社。国際経済や生産技術、人材育成、電子政府・自治体などをテーマとした書籍やムックを企画・編集。2004年、IDG Japan入社。月刊「CIO Magazine」の編集者として、企業の経営とITとの連携を主眼に活動。リスクマネジメント、コンプライアンス、セキュリティ、クラウドコンピューティング等をテーマに、紙媒体とWeb、イベントを複合した企画を数多く展開。2007年より同誌副編集長。2010年8月、タマク設立、代表取締役に就任。エンタープライズIT、地方行政、企業経営、流通業、医療などを中心フィールドに、出版媒体やインターネット媒体等での執筆/編集/企画を行っている。
Devinとは何か
私たちは皆、プログラマーであり、ソフトウェアを作ることが大好きです。創設メンバーの3人は、国際情報オリンピック(IOI)で金メダルを獲得したことがあります。好きだからこそ、ソフトウェア開発をもっと簡単に、もっと身近なものにしたいと心から願っています。そうした想いを持って、私たちはDevinを開発しました。Devinとは、ソフトウェア開発における完全自律型AIエージェントです。人間のエンジニアと同じように、状況に応じてSlackなどを活用しながら、また対話しながら、反復的に作業を行い、コードを生成します。
もちろん単にコードを生成するだけではありません。自分でそのコードを実行し、ログを確認しつつ、必要に応じてドキュメントを読み込んだり、シェルコマンドを操作したりすることも可能です。コーディングをはじめとしたソフトウェア開発のライフサイクル全体を、Devinであれば自律的にこなせるのです。
すでにDevinは、何千もの企業で実際に利用されています。特に、大規模で複雑なコードを扱うシーンで、大きな能力と価値を発揮しています。
世の中には、エンジニアがより速くコードを書くための優れた支援ツールがたくさんあります。しかしDevinは、それらとは根本的に異なるアプローチを取っています。
何が違うのかと言えば、Devinは「自ら行動する」という点、つまりは圧倒的な自律性が備わっています。タスクを一度わたせば、時間をかけてでも自分で作業を進め、完了したらその結果を教えてくれます。人間は、Devinが生成した成果物に対して、まるで同僚と仕事をするように、レビューやフィードバックを行えば良いだけなのです。
Devinに「競合はいない」
AIによるコーディング支援の領域には、素晴らしいツールを生み出している企業が数多く存在します。そして面白いことに、それぞれのソリューションは少しずつ異なる方向性を持っています。私たち自身も、どんな製品を作るべきかという点について非常に細かくこだわり抜いています。そのため、明確に「これが直接の競合だ」と言える相手は、実は存在していません。
たとえば、マイクロソフトのGitHub Copilotをはじめ、OpenAI、アンソロピック、グーグルといった企業が提供しているツールは、私たちにとっては補完的な存在です。私たちのプロダクトは、それらとは異なるまったく新しいコーディング体験を提供しており、実際にこうした企業と提携関係を築いています。
だからこそ、対立ではなく協調という形で、この分野をともに進化させていけると考えています。 【次ページ】Devinを「効果的に活用する」ための秘訣
AI・生成AIのおすすめコンテンツ
AI・生成AIの関連コンテンツ
PR
PR
PR