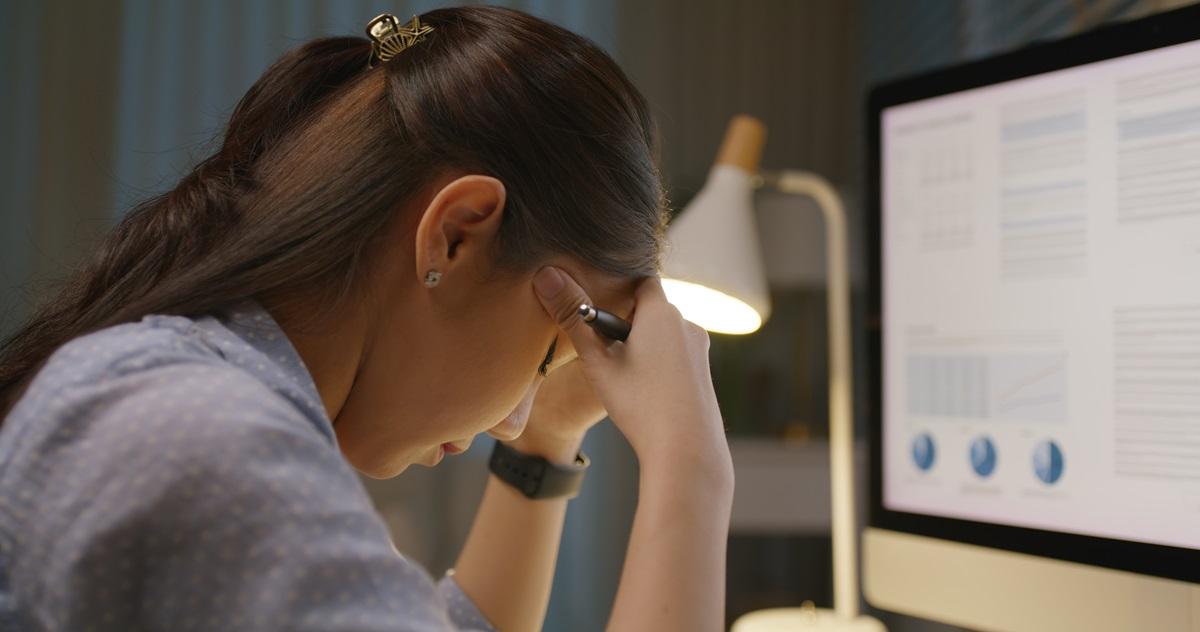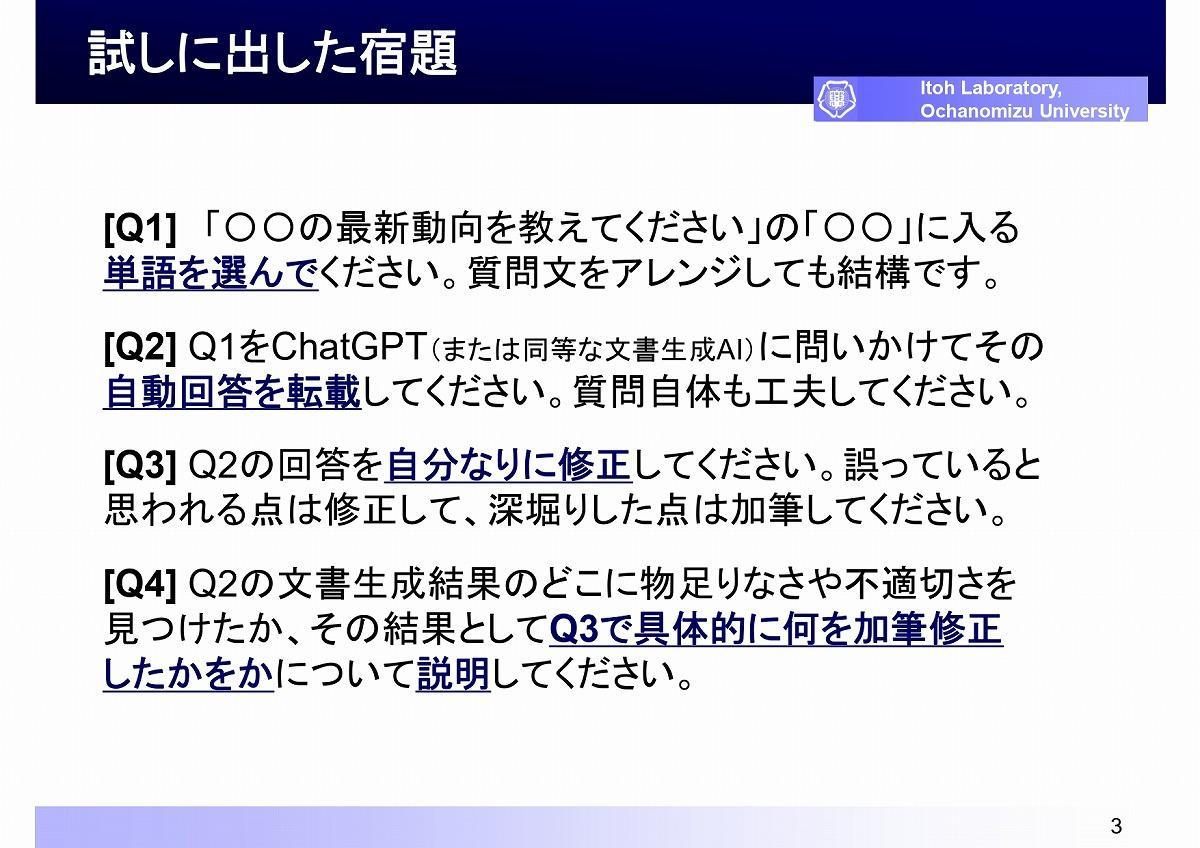- 会員限定
- 2025/07/31 掲載
これが正しい教育か?──2万3000字の論文を「AIが書いた」と判定された学生の悲劇
消費者ビジネスの視点でIT技術を論じる記事を各種メディアに発表。近年は中国のIT技術に注目をしている。著書に『Googleの正体』(マイコミ新書)、『任天堂ノスタルジー』(角川新書)など。
中国の最新技術とそれらが実現させる最新ビジネスをレポートする『中国イノベーション事情』を連載中。
すでに2023年に中国で起きていた……「AI代筆禁止」大論争
生成AIの普及により、教育現場で深刻な問題が浮上している。ChatGPTをはじめ生成AIは、調査、データ整理、思考補助のツールとしてこれ以上のものはなく、生徒や学生にも積極的に使ってもらい、活用するスキルを身につけてほしい。その一方で、課題や宿題をAI任せにして、それを写して提出するようなことはしてほしくない。どうやってAIとの正しい付き合い方を指導すべきなのか、頭の痛い問題だ。
2023年、中国で学位法の草案が公開されると、教育関係者の間で大きな議論が起きた。争点となったのは、学位論文をAIに代筆させることを禁止する条項だった。
議論になった点は大きく2つある。
1つは、AIによる代筆の線引きをどこに設定するのかという問題だ。文献調査でAIの力を借りることは問題がないが、書き上げた論文をAIで校正したり、添削をして修正することは、“セーフ”だろうか。論文の構成をAIで生成したり、難しい部分の文章を出力させる行為はどうだろう。“セーフ”と“アウト”の感覚は人それぞれで、どこで線引きをして、どうやって学生に守らせればいいのだろうか。
もう1つの問題は、AI代筆された論文を検出できるのかという問題だ。学術論文の世界では盗用などを検出するツールが以前から使われていて、現在はAI生成のテキストの検出にも対応し始めている。しかし、問題は精度だ。検出精度にはまだまだ限界があり、それで論文の掲載や受理を拒否する根拠にできるかは危ういところがある。
結局、この学位法が2024年に公布された時には「AI代筆禁止」の条項は盛り込まれず、判断は先送りされた。 【次ページ】大論争後、一部の大学が設定した「あるルール」が招いた“トンデモ事態”
AI・生成AIのおすすめコンテンツ
AI・生成AIの関連コンテンツ
PR
PR
PR