- 2017/01/17 掲載
STEM教育とは何か? アートを加えたSTEAM教育とは?成毛眞 氏に聞くAI時代の必須スキル

STEMとは何か、なぜ生まれたのか
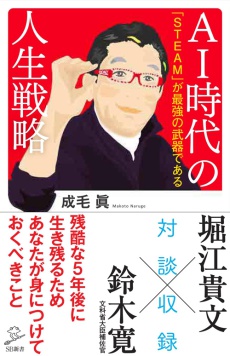
もともとアメリカの子供向け教育の概念で、アメリカ国立科学財団(NSF)が使い始めました(言葉が生まれた当時はSTMEだった)。これには理由があって、OECD加盟国の15歳の生徒を対象にした学習到達調査(Programme for International Student Assessment, PISA)でのアメリカのランキングが「読解力」24位、「数学的リテラシー」36位、「科学的リテラシー28位とあまりに悪かったので、何とかしなければ、ということで始まったのです。そのため「STEM教育」という言葉で使われることが多いです。
ただし、日本の子供のPISAの成績はトップクラスですから、実は日本にSTEM教育は必要ありません。一昨年、ある雑誌の企画で、日比谷高校で使っているすべての教科書を買って取材したのですが、驚きました。たとえば、生物Bでは遺伝子組み替えの実験をやっている。物理も超ひも理論が出てきて、量子力学と相対性理論の統合をどうすすめるかといった内容をやっている。
いま、サイエンスはどんどん変化しています。数学は以前の論理学のようになってきました。同様に物理学は数学のように、化学は物理学のように、医学は化学のようになってます。量子論を応用しないと新しい物質を作ることはできませんし、医学は化学の知識と遺伝子工学なしでは成立しなくなっている。
もともと教育の概念なので、「教育しなければ」「学ばなければ」と考えがちですが、そうではありません。たとえば、一般のビジネスパーソンが量子物理学やプログラミングを知る必要はまったくないと思いますが、ブロックチェーンは知らないとまずいことになります。おそらく、3年以内にブロックチェーンを使ってビットコインで給料を支払う会社が出てきます。
Amazon Go(注)が話題ですが、その決済が最終的にビットコインにならない理由は、どこにもありません。コンビニ、ATMやレジを製造している会社、給与振り込みのサービスを提供している会社……など、あらゆる業界が変わります。
STEMを知らない人は周りで起きていることが魔法に見える
人工知能、ドローン、VRなど、テクノロジーの進展は著しく、STEMに興味のない人は、自分の周りで起きていることが魔法に見えると思います。未来を生きる3割と残りの7割に分かれるのではないでしょうか。たとえば、テレビCMで非常にクオリティの高い空撮映像が流れるようになりました。あれはドローンで撮影しているわけですが、深センのドローンメーカー DJIがプロ用のモデルを出したのは、今からわずか2年前です。
では、これからの2年後はどうなっているでしょうか。かつて、小泉首相が乗って話題になったセグウェイは、当時、100万くらいしましたが、2015年に中国企業のシャオミ傘下のNinebot社に買収され、いまはビックカメラ7万円くらいで売られています。
iPhone 3Gが発売されたのは、今から8年前の2008年です。いまや、スマホのない生活は考えられません。これだけ急激に変化しているのです。今から数年後、どうなっているでしょうか、ということです。
ただし、STEMをゼロから学べといっているのではありません。簡単にいえば「最新の製品に触れなさい」ということなのです。

これらを組み合わせると何が起きるでしょうか。たとえば、パリのエッフェル塔にTHETAを設置すれば、世界のどこからでも現在のパリの様子をVRのヘッドセットを付けてリアルタイムに体験できます。セキュリティ会社の警備の方法も変わります。2020年の東京オリンピックの見方も大きく変わります。これは予想ではありません。数年後に訪れる確約された未来の話です。
「STEAM+SF」とは何か、どうやって身につければよいのか
最近では「STEM」に加えて、アート(芸術)やSFにも触れるべきだという意味で、「STEAM」や「STEAM+SF」という言い方をしています。アートを強調するのは、やはりアップルの存在です。アップル製品は、パッケージも含めてどれもきれいですよね。ドローンのDJIにしても、通信機器のファーウェイやシャオミにしても、中国企業のデザインは、ここ2年くらいで急激によくなっています。一方、日本企業はどうでしょうか。ただ、STEAMの知識が増えれば明るい未来が待っているかというと必ずしもそうではありません。STEAMの知識はあくまでパーツです。それぞれの関連性を見いだして、組み合わせて活用する能力が必要になる。それには「想像」と「創造」の2つの力が欠かせない。それを養うにはSFを読むのがいちばんです。だから「+SF」なのです。
こうした知識を養うには、まずはアキバに行くことです。家電店に入って、上から下まであらゆる新製品を手にとってみる。いろいろラボで体験するのもいいと思います。
ただし、体験できないものは本やネットで知るしかない。たとえば、ブロックチェーンの概念は本を読まないとわかりません。セルロースナノカーボンもそうです。あらゆる企業が大金をつぎ込んで取り組んでいるのに、一般の人はほとんど知らないのがセルロースナノカーボンです。知っているのと知らないのとでは、数年後、大きな違いになるでしょう。
ゲームは最適解を見つける脳の訓練になる
私の娘が小学校5年生のとき、地理のテストで60点しかとれなかったことがあります。内容を見てみたら、信濃川の支流の名前が答えられなくて減点されていました。他の問題も似たようなものです。それを見て、私は「100点なんかとらなくていい」と言いました。ネット時代にそんな無駄なことをやっているなら、ゲームをやったほうがいいと思います。ゲームは最適解を見つける脳の訓練です。アクションゲームも含めて、いろいろゲームをやったほうが脳には絶対いい。ゲームをやったら悪影響があるというのはナンセンスです。信濃川の支流の名前を覚えることに何の意味があるのでしょうか。こんな学習は辞めさせないと、本当に大変なことになってしまいます。
ただし、英単語だけはもっと記憶させたほうがいいと思います。小中学校では、いまの2倍、3倍の単語を覚えさせたほうがいい。日本人が英語をしゃべれない最大の原因は、単語を知らないからです。文法がわからないからでも、日本人がシャイだからでもありません。覚えている英単語の絶対数が少ないのが原因です。
子供にスマートフォンを持たせないという議論もありますが、その異様さにゾッとします。持たせないと主張する人は、これからの時代に、スマホも使えない子供を育てるつもりなのでしょうか。その子は、生きていけません。
AIに代替されない人材になるには
英オックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授が、AIの登場によって、今後、10年~20年でアメリカの総雇用者の約47%の仕事が機械に代替されると予測して話題になっています。それが誰に襲ってくるかは、誰にもわかりません。AIプログラマだけは、たぶん大丈夫だろうと言われていますが、あくまで「たぶん」です。それさえもわかりません。
これから産業構造がどう変わるか、社会がどう変わるかなんて、誰にもわかりません。それよりも大事なことは「あなたはどうするか」でしょう。国のこと、社会のことを心配する前に、自分の心配をしたほうがいい。それには、最新の製品、テクノロジーに興味を持つことです。
そうすれば、何が新しいのかわかります。ライバル企業がセルロースナノカーボンに投資をしているのに、自分の会社がしていなければ、会社を移ろうと思える。しかし、何も知らなかったら、いまの会社とともに朽ち果てるしかないのです。
人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ
人材管理・育成・HRMの関連コンテンツ
PR
PR
PR


