- 会員限定
- 2019/11/13 掲載
「阪急・宝塚・東宝」創業者 小林一三氏、34歳で「ダメ銀行員」を脱却できたワケ
連載:企業立志伝
1956年広島県生まれ。経済・経営ジャーナリスト。慶應義塾大学卒。業界紙記者を経てフリージャーナリストとして独立。トヨタからアップル、グーグルまで、業界を問わず幅広い取材経験を持ち、企業風土や働き方、人材育成から投資まで、鋭い論旨を展開することで定評がある。主な著書に『世界最高峰CEO 43人の問題解決術』(KADOKAWA)『難局に打ち勝った100人に学ぶ 乗り越えた人の言葉』(KADOKAWA)『ウォーレン・バフェット 巨富を生み出す7つの法則』(朝日新聞出版)『「ものづくりの現場」の名語録』(PHP文庫)『大企業立志伝 トヨタ・キヤノン・日立などの創業者に学べ』(ビジネス+IT BOOKS)などがある。
創業者の人生とともに世界中のトップ企業の源流を探る『企業立志伝』をビジネス+ITにて連載中。
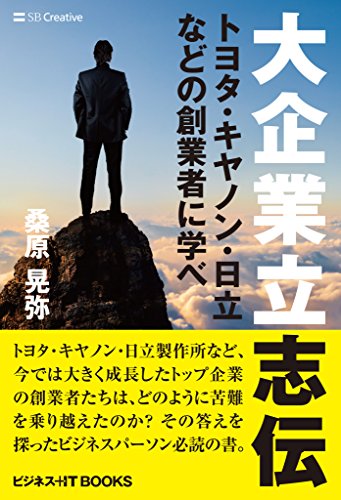
1月3日生まれ「一三」と命名

一三(いちぞう)という名前は、1月3日生まれにちなんでつけられたそうです。生まれて間もなく母親が死去、父親とも離縁されたため、当時3歳の姉・たけよと共に大叔父の家に引き取られ育てられます。
幼くして「孤児」となった小林氏ですが、小林家はもともと甲州でも5本の指に数えられるほどの豪農であり、「布屋」と号して酒造業や絹問屋(きぬといや)を営む豪商でもありました。
小林氏は数え年3歳の時から家督をついで「布屋」の主人であり、周囲からは「ぼうさん」と呼ばれ、何不自由のない生活を送っていたそうです。
作家志望の文学青年。のんきな学生時代
高等小学校から私塾成器舎を経て上京。1888年に福沢諭吉が塾長を務める慶應義塾に入学します。この時代の起業家の多くは、家が貧しくて満足に学校に行けなかったり、あるいは苦学をしたというケースが多いのですが、小林氏の学生生活は苦学とも刻苦勉励ともほど遠いものだったとうかがえます。小林氏の実家は裕福なうえに当主ですから、学生時代には半期に500円ずつ送金してもらっていたそうです。小林氏が最初に就職した三井銀行の初任給が月13円ですから、いかに恵まれていたかがよく分かります。小林氏はこのお金を使って芝居小屋に好きなだけ通い、作家志望の文学青年としてまさに自由な生活を送っています。
当時の学生としては「いかがなものか」とも思いますが、この時の経験がのちの宝塚歌劇の設立や阪急沿線の開発や販売に活かされます。人生はスティーブ・ジョブズが言うように「いつか点と点がつながると信じる」ことも大切なのだと考えさせられます。
うだつのあがらない“ダメ銀行員”時代
慶應義塾を卒業した小林氏の第一志望は新聞社でしたがかなわず、慶応出身者の多かった三井銀行に就職しています。初出勤は1893年1月からと決まっていたといいます。ところが、年末に熱海で病気療養中の友人を訪ねたまま、熱海で遊び暮らしていたそうです。「いつ東京へ行くのだ」という友人の心配をよそに、小林氏が三井銀行に出勤したのは3カ月後の4月3日のことだったというから驚きです。
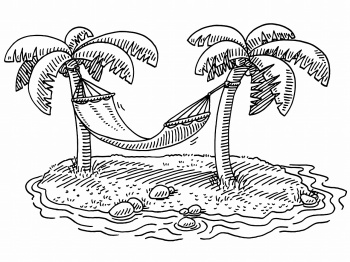
本来ならここでクビになってもおかしくないところですが、小林氏の推薦者は高橋義雄という超大物でした。
そのおかげもあり、何とかクビがつながったそうです。しかし、この時から小林氏の銀行員生活にはマイナスの評価がつきまとうことになります。
元々が作家志望で、裕福な家の生まれの小林氏にとって銀行での仕事は興味の湧くものではありませんでした。
生家からの仕送りで茶屋遊びにうつつを抜かす日々を送っていたそうです。本店秘書課から大阪支店、名古屋支店などを渡り歩きます。その後、1900年1月、三井銀行が東京深川支店所属倉庫を分離して新設することになった箱崎倉庫の主任として栄転が決まります。しかし、なぜかその辞令が一夜にして撤回され次席に格下げされたうえ、1年半後には本社調査課へと左遷させられたといいます。
ここでの生活は小林氏にとってやりがいのないものだったようです。1907年、大阪支店時代の支店長で敬愛する岩下清周(きよちか)氏が設立する大阪北浜銀行傘下の証券会社に参加するため長年勤務した三井銀行を退社する決意を固めた小林氏は当時の心境をこう語っています。
「明治34年1月、勇んで東京へ来て、支配人になりそこねて、それから足掛け7年、紙屑籠の中に長く長くくすぶって暮らしてきたのだから、これ以上の辛抱はと、私はだんぜん三井を辞めることを決心したのである」(『逸翁自叙伝』p131)
小林氏は上司に辞意を伝えますが、「もう少し辛抱したまえ」と言われたものの、実際には「少しも惜しまれておらない」と感じたというほどその退職はあっさりしたものでした。
“お荷物”な鉄道会社の監査役へ
こうして銀行員生活を終えた小林氏ですが、1907年1月、大きな期待を胸に大阪へと到着したその日、運悪く日露戦争の戦争特需の反動から株式相場の大暴落が始まり、証券会社設立の話は流れてしまいました。頼りの岩下氏に会うこともできない小林氏は大阪で無為な日を送るしかありませんでした。幸い退職金もあれば、生家も裕福であり、日々の暮らしに困るという心配はありませんでしたが、それでも何もすることがないという「浪人」の境地は恐ろしくてならなかったといいます。このような言葉を残しています。
「暗黒の境地とは、こういう状況なのか」(『鬼才縦横』上p373)
やがてそんな小林氏を心配して岩下氏が訪ねてきます。そのときに紹介してくれたのが阪鶴鉄道(現在のJR福知山線)の監査役の仕事でした。軍港のある舞鶴と大阪を結ぶ鉄道会社ですが、当時は業績も芳しくなく、支援する三井物産にとっても完全なお荷物会社でした。
いずれは鉄道国有化法によって国有化される予定でしたが、同社幹部は電化路線の新会社「箕面有馬電気軌道」を立ち上げようとしていました。
しかし、岩下氏によるとその計画は難航しており、小林氏には「(国有化される)阪鶴鉄道の葬式をすることではなく、新会社の産婆役になる」(『鬼才縦横』上p391)という厄介な役割が期待されていました。
小林氏に鉄道事業の経験はありません。
それでも小林氏は「とにかくお引き受けして、全力を尽くしてみたいと思います」(『鬼才縦横』上p393)と返事をします。
ここから小林氏の経営者としての人生がスタートすることになりました。
【次ページ】いよいよ伝説の経営者・小林一三の人生がはじまる
リーダーシップのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR




