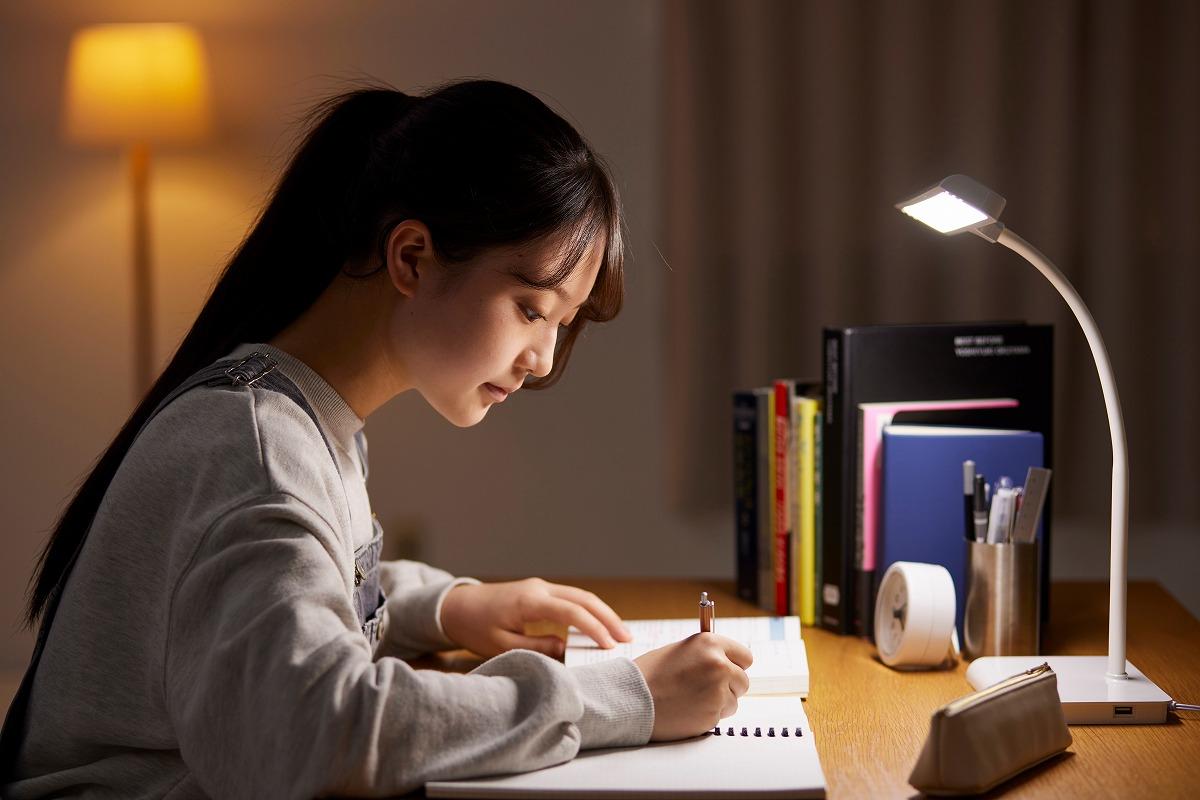- 会員限定
- 2025/08/17 掲載
イチロー氏も実践していた、業務パフォーマンスのムラをなくす「習慣化」の底力
言語学者(法言語学、心理言語学)。明治大学教授。1991年、東洋大学文学部英米文学科卒業。1999年、シカゴ大学言語学部博士課程修了(Ph.D. in Linguistics、言語学博士)。2000年、立命館大学法学部助教授、2005年、ヨーク大学オズグッドホール・ロースクール修士課程修了、2008年同博士課程単位取得退学。2008年、明治大学法学部准教授。2010年、明治大学法学部教授。司法分野におけるコミュニケーションに関して、社会言語学、心理言語学、脳科学などのさまざまな学術分野の知見を融合した多角的な研究を国内外で展開している。また、研究以外の活動も積極的に行っており、企業の顧問や芸能事務所の監修、ワイドショーのレギュラー・コメンテーターなども務める。著書に『特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ』(クロスメディア・パブリッシング・共著)、『科学的に元気になる方法集めました』(文響社)、『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)など多数。
前編はこちら(この記事は中編です)
人間の行動の45%はルーティン化され、無意識に実行している
デューク大学のニールらの研究によると、「人間の行動の約45%が習慣化された行動」だといいます。つまり、私たちの行動の約半分は、ルーティン化されたもので、無意識のうちにその行動をチョイスしているということ。面倒くさいことでも習慣にすれば、たとえ複雑な行動も自動化され、ラクに実行することができるのです。
では、自動化とは何でしょうか? 字を書くことを一例に説明しましょう。
「字を書く」という行為、当たり前に見えて実は…
字を書く行為は、ほとんどの人が幼稚園ぐらいから書きはじめ、自分の書体が完成するのは中学生から高校生くらいと言われています。10年近くかけて字を学び、自分の中に落とし込むことで、自分だけの筆跡ができ上がります。文字を書くという作業は、さまざまな体の部位を連動させるアクションです。それと同時に、書いたものを感触と視覚でチェックし、微調整を行います。
書くという作業は当たり前に見えて、実はとても複雑で高度なアクションによって成り立っているわけです。それだけ高度な作業のため、自分だけの筆跡として落ち着くまでに非常に長い年月がかかってしまうというわけです。
ところが、これだけ複雑な筋肉と骨格の連動も練習を重ねるにつれ、それほどの苦労ではなくなり、簡単に文字を書けるようになるから不思議だと思いませんか?
これこそが「自動化」の効力です。むしろ、自動化されると今度は変えにくくなってしまい、ひと目見て「これは自分の文字だ」と認識できるほど定着してしまいます。
複雑なことですら繰り返し続けると自動化され当たり前になる。そうなれば、こちらのものです。あれだけ最初は億劫だったことも習慣として定着するわけです。
イチロー氏の変わらないパフォーマンスを可能にしている行為
元プロ野球選手のイチローさんがベンチを出てから打席に立って構えるまでの一連の動きのような、“一定の順序やリズムで同じことをする行為”をルーティンと呼びます。ルーティンを繰り返すと、脳内に「そのアクションをするということは……」と専用の回路がつくり出されます。
その結果、体に叩き込まれていることを発揮しやすくなり、普段の練習でも緊張をともなうような本番でも変わらないパフォーマンスを可能にするわけです。
仕事のパフォーマンスを上げることも同じです。繰り返し行って自動化(=ルーティン化)させてしまえば、パフォーマンスにムラが生じづらくなります。
仕事における習慣化とは、自分のルーティンをつくることという意識をもつとより効果的でしょう。
業務効率化のおすすめコンテンツ
PR
PR
PR