- 会員限定
- 2016/05/31 掲載
赤羽雄二 氏「“結果を出せる人”は、本の読み方が違っている」(2/2)
視野が狭い人は目先のことしか考えられない
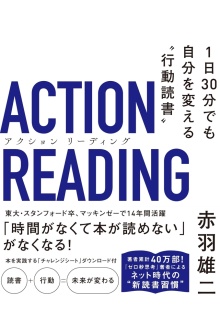
※クリックするとアマゾンのページにジャンプします。
私が見ているなかでも、視野が広い人であれば、社長方針あるいは部門長方針を聞いて、自分の仕事を全社最適の観点から考え、行動を起こすことができます。二歩も三歩も先を見て、最も効果的な手を打つことができるのです。
一方、視野が狭い人は、目先のことしか考えません。上司がどれほど目線の高い話をしても、自分が理解できる範囲でしか物を見ようとせず、考えようとしません。要は他とのつながりのない「点」でしか物を見ていないので、一貫性を持った施策や行動につなげることができないのです。すると、やることが行き当たりばったりになりますし、環境が変わったらおろおろするだけになるでしょう。また、そういう人は、他部門との連携はできるだけしないようになります。調整しづらくて面倒だからです。
どちらが結果を出せるか、社内でも有能な人として活躍できるか、は明確ですよね。
同じテーマでも、さまざまな視点で書かれた本があります。
「人工知能」一つにしても、
「人工知能はこれからどう発展するのか」
「人工知能が心を持つ可能性はあるのか」
「人工知能は人の職を奪うのか」
「人工知能の技術はどういうものなのか」
など、それぞれ切り口が色々とあります。会社の問題についても、
「経営者向けの本」
「リーダー向けの本」
「中堅向けの本」
など、見ていくと、立場によって状況が変わることがわかります。そうして関心があるテーマについてさまざまな本を読むと、「さまざまな視野で物事を考える」ことができるようになり、会社やクライアントの方などからも、「広い視点でアイデアを出してくれる」「必要なことをわかってくれる」大事な人材だ、と思ってくれるようになるのです。
読書を行動に変える仕組みとしてFacebookグループ「アクションリーディング 行動するための読書」を立ち上げています。そこでは、皆さんの「読書体験」を共有したり、読書をもとにどう行動するかやり取りができればと思います。もちろん、質問も大歓迎です。ぜひ、ご登録ください(赤羽 雄二)。
Facebookグループ「アクションリーディング 行動するための読書」へ
人材管理・育成・HRMのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR


