- 会員限定
- 2015/09/14 掲載
武田砂鉄氏インタビュー:なぜメディアには「全米が泣いた」ばかり溢れているのか
『紋切型社会』著者に聞く
-
|タグをもっとみる
言語ではなく、社会の問題
──まずは『紋切型社会』を執筆したきっかけについてお聞かせください。武田氏:編集者と、テーマについて打ち合わせを重ねる中で、「気になるフレーズを並べ、そのフレーズから広げていく評論を書いていこう」と、かなり漠然としてはいるものの、方向性が定まりました。この本には20のフレーズが入っていますが、普通だったら100くらい考えてから、書きやすい20に絞るはずです。でも今回考えたのは、22くらいでした(笑)。フレーズを入口に用意して、そこから踏ん張って掘り下げてみようと。結果として、グルグル旋回していくような考察になったのは、「とにかくこの20のフレーズから考え込む」って決めて書いたからなんです。タイトルを付けるのには苦労しまして、編集者と50~60案ほどは考えましたね。
──フレーズの数より多いですね。
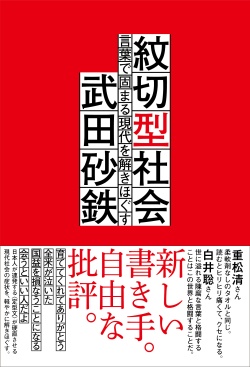
──言葉に限らず、そこから広がる部分が大きいと。
武田氏:はい。目次を見て「うんうん、この言葉使っちゃうよねー」と“あるある”な感じで捉えられることも多いんですが、「この言葉を使っちゃダメ」と言葉狩りをしているわけではありません。それは読んでくだされば分かると思います。限られた言葉を使うことによって選択肢が失われてしまい、社会の見え方や、個々人の考え方が狭まることへの危惧を通底させたつもりです。
影響を受けたナンシー関と小田嶋隆
武田氏:本を書いているときに全く予想していなかったのは、この本のテーマに合わせる形で、安倍政権についてのコメント依頼がかなり来たことですね。現在、安保法制についての議論が進められていますが、その中で、例えば「(ポツダム宣言を)つまびらかに読んでいない」「私は総理大臣なんですから」「早く質問しろよ!」など、安倍首相の言葉が注目される機会が増えてきました。新聞などで安倍首相の言葉を一つひとつ検証する動きが出てきて、「こういう本を書いた人は安倍首相の言葉をどう思うのだろうか」とコメントを求められる機会が増えました。そのコメント記事から本書の存在を知って手にとってくださった方もいたようで、書いた時点ではこのような反響が起こるとは思っていませんでした。
──言葉に引っかかるようになったのは子どもの頃からですか?
武田氏:そうですね。生まれてこのかた、そんなに性格が素直ではないんです(笑)。中高時代はクラスの階層をABCだとすると、Bの下くらいに位置していました。最下層には下がりたくないし、だからといって上の層はイケイケで馴染めないし、「なんかちょっと面白いことたまに言う奴」みたいなポジションで、時たまAのところへ面白いことを言いに出向くような立ち回りでした。深夜ラジオを聞いたりして、自分の中だけで楽しむための言葉を生み出して、自分で消費していく、という状況でしたね。他のみんなは電車通学で僕だけ自転車通学だったので、下校時にクラスメイトが吉祥寺に寄って女子とカラオケをしている頃、僕は自転車でブックオフに寄って「おっ、別冊宝島が安くなってる」とか言いながら(笑)、色んな本を買って帰っていましたね。
──文章を書く上で、影響をうけた書き手はいますか?
武田氏:コラムニストのナンシー関さんや小田嶋隆さんには、大きな影響を受けています。今、芸能人評を書くときにナンシーさんの本は絶対読まないようにしていますし、『紋切型社会』のような社会時評を書くときは小田嶋さんの本や記事を読むと影響されてしまいそうなので、注意しています。
【次ページ】イメージをどんどん踏み外したい
おすすめコンテンツ
PR
PR
PR


