- 会員限定
- 2018/06/29 掲載
ファナックが買収したライフロボティクス、創業者の尹祐根氏に聞いた11年間の歩み
森山和道の「ロボット」基礎講座
フリーランスのサイエンスライター。1970年生。愛媛県宇和島市出身。1993年に広島大学理学部地質学科卒業。同年、NHKにディレクターとして入局。教育番組、芸能系生放送番組、ポップな科学番組等の制作に従事する。1997年8月末日退職。フリーライターになる。現在、科学技術分野全般を対象に取材執筆を行う。特に脳科学、ロボティクス、インターフェースデザイン分野。研究者インタビューを得意とする。
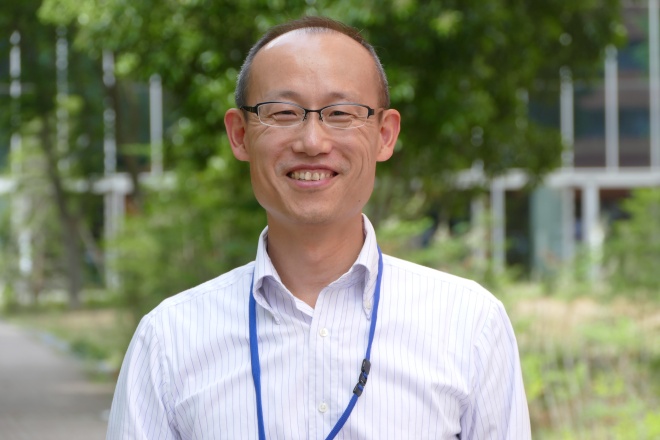
情報・人間工学領域研究戦略部 連携主幹
尹 祐根氏
ライフロボティクス社創業者
地味に違和感なく現場に溶け込む協働ロボット
「CORO」の特徴は変形伸縮する「トランスパンダー」機構にある。複数のブロックが連結することでリンクを伸縮させる独自の仕組みで、肘に相当する関節がないために周囲とぶつかることなく、同時に、広い動作範囲を実現している。
小型といってもフットプリントもそれなりにある。洗浄済みの丼を移すだけのロボットだが、首を伸ばして覗き込んで見ていると「ちゃんと動いているときは結構使えますよ」と店員さんが教えてくれた。良い意味で普通に、地味に、違和感なく動いていた。
2016年1月から販売を開始した「CORO」は、吉野家のほか、ロイヤルホストやトヨタ、オムロン、化粧品のコスメナチュラルズなど各社で、外観検査、ピッキング、搬送作業を手伝うための協働ロボットとして用いられている。それ以外の企業でも使われているようだが、公開されていない。
ライフロボティクス社の創業は2007年。コア技術は前述の「トランスパンダー」機構である。創業当時は介護を主なターゲットとしており、筋ジストロフィーや頚椎損傷などによって上肢に障害がある人の自立補助を用途として、電動車椅子に適用するロボットアームとして可能性を探っていた。それが2014年ごろに分野を変え、産業用の協働ロボットへとピボットした。
なお協働ロボットとは、従来の柵の中で作業するロボットとは異なり、人と空間を共有して働くロボットである。「Collaborative Robots」の略で「co-bot(コボット)」などとも呼ばれ、人手不足を背景に2015年ごろから急激に注目を集め始めた。柵なしで使えるためロボットの占有面積が少なく、中小企業での採用も期待されている。
長年苦労していたライフロボティクスも時流に乗って業務を拡大し始めた----と思っていたら、ファナックへのバイアウトというかたちによって、予想以上の速さでイグジットとなった。
ライフロボティクスのファウンダーである尹氏は、今回のファナックによる買収は「関係者全員にとってハッピーな結果だった」と語る。投資家たちにも「事業が一番伸びる、スピードが上がる選択を取ります」と伝えていたという。
「たとえば僕が社長じゃない方が事業が伸びるなら社長を降りるし、IPOは目指しますが、素晴らしい話が来たらM&Aもありですよと。だからバイアウト大前提ではありませんでしたが、とにかく、事業が一番伸びるやり方を選びたいと常に考えていました」
同社が協働ロボット事業を始めた後は海外企業を含めて色々な話が来ていたそうだが、会社を売る相手としてファナックを選んだ理由については「彼らと組むことが一番事業が進むということと、働いている社員にとって、待遇も含めて良い状態に持っていけること。そして、お客さんにとっても一番安心できる会社かなという判断をしました」。確かにそうかもしれない。
買収の話が本格化した時期などについては現時点では公表されていない。買収に関しては、これ以上のコメントはもらえなかった。
2018年6月26日、日経BP社「日経Robotics」ならびに日本経済新聞にて、ファナックがライフロボティクスの「CORO」を顧客から回収してファナック製協働ロボットに置き換えているという報道(日経Robotics、日本経済新聞)があった。
ライフロボティクス社内でも品質管理は行っていたとのことだが、一ベンチャー企業の基準では、産業用ロボット最大手のファナックの基準を満たす製品レベルには達していなかったということだろう。
なおユーザーがCORO利用の継続を希望する場合はファナックが保守を続けるという。品質向上には時間がかかる。複雑な機構を持つ「CORO」が十分な品質を満たすには、まだまだ時間がかかりそうだ。ロボット技術ベンチャーの立ち上げが難しい理由の一つは、ここにもある。
一方、そのファナックがベンチャーのライフロボティクスを買収したことも事実だ。「CORO」そのままのかたちで、たとえばロボットがファナック色に染められただけで出てくるようなことは当分なさそうだが、今後どのようなかたちでファナック社内でライフロボティクスの技術が熟成されていくのか。その見極めには、まだまだ時間がかかりそうだ。ロボット技術にはとにかく時間がかかる。
暗中模索の創業期を経て、協働ロボ領域へ

そもそも、なぜ研究者である尹氏が自ら起業に至ったのだろうか。
尹氏は最初から起業を考えていたわけではない。ロボットアームの研究者がついに起業に至った理由は「違和感」だったという。
「当時は介護ロボットをやろうと思っていました。ロボットを作って、ユーザーの方に使ってもらって評価実験をやるんです。ですが、やっているうちに違和感を感じました。ユーザーの方々は『この技術で自分たちの人生が変わるかもしれない』という期待を持って協力してくれるんです。でも研究では実験するだけで商品化にはまったくコミットしないわけです。評価実験というのはそういうものですので。ある意味、夢だけ見せている。それにとても違和感を感じました。人として、それってやっちゃいけないんじゃないの、と思ったんです」
商品にする努力もせずに「いや、商品化は自分たちの仕事の範疇じゃないから」と言うのは、倫理観的に強い違和感があったのだという。それで、まずはさまざまなところに実用化の打診をした。だが、ことごとく断られたという。
それで「もう、自分でやるしかない」と判断した。当時はまだ産総研内の縛りが厳しかったため、創業時は尹氏はCTOに就任し、CEOは尹氏に共鳴した人に手伝ってもらうかたちを取った。当時は産総研の職との兼業だった。
だが初めてのビジネスは甘くなかった。
「すごく厳しかったです。何も知らない状況でしたし、支えてくれる人もあまりいなかったので、とにかく全てがうまくいかなかった」
ライフロボティクスは2007年から2014年ごろまでは売り上げがまったくなく尹氏自身も無給で働いており、ほぼ一人だけでビジネスとロボット開発を進めていた。ただ、創業から6,7年間も売り上げがまったくなかった状態が続いていたにも関わらず「やめるという発想はなかった」という。なぜだろうか。
「やめなくちゃいけない状況には追い込まれてなかったので。社員も雇ってなかったし」
介護用途として開発していたロボット「RAPUDA」の技術をもとに、学術研究者向けのプラットフォームロボット「RAINOU」と、産業用を想定した「NECO-II」を発表したのは2014年だ。
「それまでずっと介護一本でやってきたんだけど、どうも介護は厳しいなと。それと『このロボットを工場で使えないか』という話もちょっとあったんですよ。2010年に入ってからかな。パラパラとそういう話がありました」
当時は、基盤のハンダ付け検査のデモを展示会などで行っていた。
ちなみに海外ではデンマークのユニーバーサルロボット社が2005年に創業され、2009年に最初のロボットである「UR5」を出している。日本の川田工業(現在はカワダロボティクス)が双腕の協働ロボット「NEXTAGE」を発表したのも2009年だ。ロボット業界全体で「協働ロボット」という言葉が使われ始めた時期である。
「僕らがやっていることも、実はそっちの方がいいんじゃないかなと言いながらやっていたんです」。ただし当時はまさに暗中模索で「ふらふらしている状況だった」という。「今ほどロボットブームじゃなかったですし、『ロボットに投資する人はいない』と言われていた状況だったですしね」
どのようなロボットを開発していたか詳細も、今では覚えていないそうだ。そのくらい悩んでいたし、今となって見ると昔の話だということだろう。
事業領域を協働ロボットへと変えるにあたって、尹氏は2014年1月、産総研を休職し、一旦離れる決断をした。
「いろいろ調べて『どうもこっちだね』というのが見えてきたので、協働ロボットにガチで行こうと。本気でやらないと、もう遅いよねと判断しました」
そしてCEO兼CTOに就任した。ハードウェアとソフトウェアのエンジニアも募集し、「NECO-II」は「CORO」というロボットへと発展して商品化された。協働ロボットに用途を転じたからといって、状況が直ちにガラッと変わったわけではなかった。だが、勝負するフィールドはここだと決めたわけだ。
生死の境目、国際ロボット展
なおライフロボティクスは、2016年3月8日にはシリーズAで約5億円の第三者割当増資を完了、2016年11月にはシリーズAおよびシリーズB含めて総額15億円の資金調達を1年間で完了したと発表されている。
大型出資を取り付けるにあたっては「もうひたすら、投資家めぐりをしました」。
「産総研発ベンチャーということもあり、以前から、投資家からのコンタクト自体はたくさんあったんです。ですが具体的な話になっていなかった。それで、そろそろ本格的にやろうというので、動き始めたんですね。とにかくツテを使って紹介してもらって。あるものは全部使う状態です」
しかし、話はそう簡単には進まなかった。
「ことごとく断られました。ソフトウェアと違ってハードウェアは大変なので、ほとんどの投資家はノーでした」。だが、捨てる神あれば拾う神ありだった。
「その中で、NTVPの村口和孝さんと、グローバル・ブレインの百合元安彦さんだけは、『こういう技術こそがすごいんだ、市場があるんだ』と言ってくれたんです。当時は日本では、この二人だけがそういう評価をしてくれて、素早く意思決定してくれました。そこからガーッと動き出したんです」
そして尹氏は、2015年12月に行われた「国際ロボット展」で勝負に出た。それまで直動伸縮機構としか言っていなかった独自機構に対して「トランスパンダー」という名前を編み出し、ロボット展では大きなブースを構えて、大々的なデモを行ったのである。
「あれが生死の境目の一つだったと思います。あそこでドーンといかなかったらダメだったでしょうね。国際ロボット展は2年に一回しか行われません。協働ロボットのマーケットも一気に来始めていました。でも、2年前の2013年の時だと、まだそういう状況ではなかった。逆に2年後の2017年のタイミングだと大手が入っちゃいましたから遅かったと思います。ピンポイントでした。今振り返っても、ピッタリはまったなと思います。勝負をかけて良かったなと思います」
ロボット展への出展後、本当に本格的に色んな商談が来たという。
「いろんな人が紹介してくれるのも、そこから始まりました。『こういう困ってる人がいるので一回会ってみないか』とか。『そのロボット使えると思うんだけど1回話してごらん』とか。問い合わせも会社にたくさん来ました。展示会はとにかく大事だったと思います。なかでも国際ロボット展は集客数も多くロボットが展示の中心ですので、圧倒的に大事だったと感じています」」
その後の展開は冒頭で述べたとおりだ。今後、活用事例が徐々に公開されていくのだろうと思っていたら、あっという間にファナックに買収されるという展開になった。
今振り返ってどう思うのか、改めて聞いた。
「やっぱり、時流にうまく乗れたというのが大きいですね。半分、運だと思います。たぶん、うまくビジネスをしてる人って、そのタイミングをつかんだ人だと思います。タイミングをつかまないと、良い技術だろうと何だろうとうまくいかないので。タイミングが大事だと思います」
【次ページ】産総研に戻った尹氏が語るロボット業界展望と、起業家へのメッセージ
ロボティクスのおすすめコンテンツ
ロボティクスの関連コンテンツ
PR
PR
PR



