- 会員限定
- 2019/03/07 掲載
田畑政治が「競泳王国ニッポン」を作るまで “諦めなかった男”の生涯
連載:「企業立志伝」番外編 日本水泳連盟会長 田畑政治氏
1956年広島県生まれ。経済・経営ジャーナリスト。慶應義塾大学卒。業界紙記者を経てフリージャーナリストとして独立。トヨタからアップル、グーグルまで、業界を問わず幅広い取材経験を持ち、企業風土や働き方、人材育成から投資まで、鋭い論旨を展開することで定評がある。主な著書に『世界最高峰CEO 43人の問題解決術』(KADOKAWA)『難局に打ち勝った100人に学ぶ 乗り越えた人の言葉』(KADOKAWA)『ウォーレン・バフェット 巨富を生み出す7つの法則』(朝日新聞出版)『「ものづくりの現場」の名語録』(PHP文庫)『大企業立志伝 トヨタ・キヤノン・日立などの創業者に学べ』(ビジネス+IT BOOKS)などがある。
創業者の人生とともに世界中のトップ企業の源流を探る『企業立志伝』をビジネス+ITにて連載中。
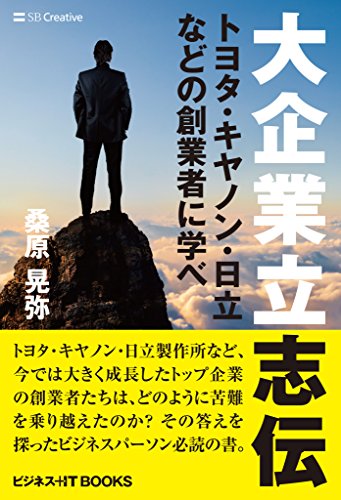

中央左は朱仄・中華全国体育総会代表団長。左端は竹田恒徳 IOC理事。
選手生命が絶たれても枯れなかった情熱
田畑氏の家族は夏にはこの別荘で暮らすのが常であり、田畑氏も夏休みには別荘で暮らし、目の前の海水浴場で泳いでいました。夏の間、毎日泳ぎ続けていた田畑氏は中学校に進むと自然と水泳部に入り、他校の学生とも合宿するほど水泳にのめり込みます。しかし、4年生のときに大腸カタルにかかり、「このまま水泳ばかりしていると、腸結核になるぞ」(『金栗四三と田畑政治』p77)という医師の忠告により、大好きな水泳を止めることになりました。
当時の日本ではまだ古式泳法が盛んに行われていましたが、明治の半ばから後半にかけて各地でプールがつくられるようになり、次第に西洋式の競泳大会も開催されるようになりました。田畑氏もいずれは競泳選手として大会に出場することを夢見ていましたが、その夢は病気によって断たれたのです。以後は、自分が選手として活躍するのではなく、後輩たちを鍛えて浜名湖の水泳を日本一にしたいと考えるようになりました。
そう考えた田畑氏はすぐに行動を起こします。まず、弁天島の海水浴場を本拠にしているほかの中学校の代表者たちと話し合い、4つの学校と協力して「浜名湾遊泳協会」を設立します。そして田畑氏は古式泳法の代わりにクロール泳法を導入。1日に何キロも泳がせるスパルタ指導によって後輩を鍛え上げていきました。
やがて第一高等学校から東京帝国大学、朝日新聞社と進んだ田畑氏。当時としては最高のエリートコースを歩みながらも、水泳の指導にはさらに情熱を傾けていきます。地元の有力者と折衝し、浜名湖の海水浴場の一角に長さ100メートル、幅30メートルのプールを作ったり、1921年には各地の強豪を招いて全国競泳大会を実施したりしていました。このとき、田畑氏はまだ20代です。
田畑氏は若いときから政治力、交渉力にずぬけたものがあった上、後年に「水泳のために実家の資産を食いつぶしたよ」と振り返るほど、資金面でも大きな貢献をしています(『金栗四三と田畑政治』p85)。そんな田畑氏の努力もあり、浜名湾遊泳協会は全国水泳大会で日本一となりますが、彼の目は早くも世界へと向けられていました――。
「日本の水泳を世界一に」という野望
日本人が初めてオリンピックに参加するのは1912年の第5回ストックホルム大会ですが、競泳種目での初参加は1920年の第7回アントワープ大会です。アントワープ大会には2人の選手が参加しましたが、いずれも予選落ちで、世界との力の差は歴然でした。世界との力の差を埋め、いつか世界の頂点に立つ選手を生み出したいと考えた田畑氏は、さらに水泳の指導に力を入れるようになります。小学生を集めて講習会を開いたり、指導者向けのテキストを作成したりするなど、水泳の一層の普及に努めたのです。さらに20代の若さで大日本水上競技連盟(後の日本水泳連盟)の理事に就任し、選手を育てるための組織の強化に取り組みました。
こうした努力が実を結び、1928年の第9回アムステルダム大会では男子200メートル平泳ぎの鶴田義行選手が初めて金メダルを獲得。ほかにも日本代表では4x200m自由形リレーで銀メダル1個、100メートル自由形で銅メダル1個を獲得しました。しかし、田畑氏はこれだけでは満足しません。神戸港に帰港した選手たちと話をした田畑氏は、選手たちからの「次は(アメリカに)勝つ」という意気込みを聞いて、こう決意します。
「これなら勝てる。目指すは4年後のロサンゼルスオリンピック。ここで日本の水泳を世界一にする」(『金栗四三と田畑政治』p98)
田畑氏は目標実現に向けて充実したプールを建設し、優秀なコーチを招聘(しょうへい)し、遠征費用などの捻出に奔走します。その結果、自ら総監督となって乗り込んだ第10回ロサンゼルスオリンピックでは、金メダル5個、銀メダル5個、銅メダル2個という快挙を成し遂げています。そして続く第11回ベルリンオリンピックでも金メダル4個、銀メダル2個、銅メダル5個を獲得。「競泳王国ニッポン」を世界に知らしめています。
そんな活躍する日本人選手や選手に声援を送る人々を見ながら田畑氏は、「やっぱりオリンピックはいいものだな、いつか日本でも」と考えるようになったといいます(『金栗四三と田畑政治』p99)。
【次ページ】敗戦失意の日本に希望を与えたい、東京五輪にいたるまで
リーダーシップのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR



